中国船の尖閣領海侵入激増が暗示する「想像したくない近未来」
8/4(火) 6:31配信
昨日(8月3日)、『産経新聞』が一面トップで、「中国、尖閣に漁船団予告 16日の休漁明けにも」と題した、おどろおどろしい記事を掲載した。
【写真】中国の「南シナ海人工島」をトランプが爆撃破壊する可能性
〈 中国政府が日本政府に対し、尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺での多数の漁船による領海侵入を予告するような主張とともに、日本側に航行制止を「要求する資格はない」と伝えてきていたことが2日、分かった。16日に尖閣周辺で中国が設定する休漁期間が終わり、漁船と公船が領海に大挙して侵入する恐れがある…… 〉
中国公船の尖閣諸島の接続水域への進入は、4月14日から連続111日となった(8月2日現在)。2012年9月に日本政府が尖閣諸島を国有化して以降の最長連続記録を更新中だ。
では、その前は来ていなかったのかと言えば、そんなことはない。海上保安庁のホームページで確認すると、今年に入って来ていないのは、1月28日、29日、30日、31日、2月1日、17日、18日、3月5日、4月12日、13日の10日間だけだ。
1月末から2月初旬の5日間は、春節(1月25日の旧正月)休みだったのかもしれない。2月中旬は、新型コロナウイルスが中国側で蔓延していた頃だ。
これでは、海上保安庁の苦労は大変なものだろう。12カイリの領海への中国公船の侵入も、今年に入って計16日、延べ52隻に及んでいる(7月30日まで)。直近では、7月14日に4隻もの中国公船が、尖閣諸島の領海に侵入している。
これはもう、新たなステージに入ったと捉えるべきだろう。すなわち今後、尖閣諸島の海域が平穏になることはなく、逆にますます中国側の行動はエスカレートしていくと考えていた方がよいということだ。冒頭の『産経新聞』の報道も、そうした中国の傾向を裏付けている。
中国海洋調査船の「怪しげな行動」
海上保安庁のホームページでは、尖閣諸島近海ばかりか、沖ノ鳥島の近海でも、中国公船の不穏な動きを伝えている。
例えば7月9日には、「中国海洋調査船『大洋号』の視認について(第1報)」として、次のように発表している。
〈 1 本日、午前10時40分頃、しょう戒中の当庁巡視船が沖ノ鳥島の北北西約310キロメートルの我が国排他的経済水域内において、漂泊中の中国海洋調査船「大洋号」がワイヤー様のものを海中へ延ばしているのを確認したことから、「我が国の排他的経済水域において、我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を無線及び電光掲示板(停船命令等表示装置)にて実施しました。
2 本日、正午現在、同調査船は沖ノ鳥島の北北西約310キロメートルの我が国排他的経済水域内に漂泊しており、当庁巡視船が監視警戒にあたっています。〉
沖ノ鳥島は、小笠原諸島に位置する日本最南端の島である。東京湾から南へ1734km下ったところにある。北小島が7.86㎡、東小島が1.58㎡しかなく、日本は灯台を建てたり、消波工事を行ったりしている。
そこで7月9日以降、中国海洋調査船は、次々と「怪しげな行動」に出ており、それらの詳細を、海上保安庁は日々、発表している。そして、7月18日に出された最後の「第10報」は、以下の通りだ。
〈 1 中国海洋調査船「大洋号」の昨日(17日)午後2時以降の動静は、本日午前11時頃、沖ノ鳥島の南約270キロメートルの我が国排他的経済水域内において、昨日(17日)午前9時20分頃、船尾から海中に投入した観測機器様のものを揚収しました。
同調査船が観測機器様のものを揚収するまでの間、当庁巡視船から「我が国の排他的経済水域において、我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を無線及び電光掲示版(停船命令等表示装置)により実施しました。
2 その後、同調査船は同位置から南西方向に航行し、本日午後5時41分頃、沖ノ鳥島南南西約370キロメートルにおいて、我が国排他的経済水域を出域しました。
3 以後、同調査船の動静に特異動向を認めなければ、本報をもって最終報といたします。〉
戦後75周年の抗日キャンペーン
中国国内でも新たな動きがある。それは7月20日、中国中央広播電視総台(CCTV)の朝のニュース番組『朝聞天下』で、「浴血抗戦 歴史豊碑」(血を浴びた抗日戦争、歴史となった豊富な碑)と題したシリーズの特集番組を、この日から放映し始めると報じたことだ。
CCTVのショートカットの美人キャスター、天亮(Tian Liang)が、厳めしい顔つきで、次のように述べた。
「今年は中国人民が、抗日戦争及び世界反ファシズム戦争に勝利して75周年です。いまから89年前の『9・18』の砲火から、83年前の盧溝橋の硝煙まで、戦争は中華民族に、生死存亡の空前の苦難をもたらし、数千万人の同胞が苦難に巻き込まれ犠牲になったのです。
しかしながら、苦難は必ずしもわれわれが攻撃されて倒れることではありません。無数の先烈の勇士が不屈の抗争を引き継ぎ、われわれの血肉でわれわれの新たな万里の長城を築きました。これらはすでに、わが民族の永久不滅の精神の記憶と激励になっています。
中国人民の苦しくも卓越した抗日戦争もまた、世界の反ファシズム戦争の不可分の一部であると公認されており、重要な東方の戦場だったのです」
彼女の説明中、「われわれの血肉でわれわれの新たな万里の長城を築く」というフレーズは、中国人なら誰もが知っている中国国歌『義勇軍行進曲』の一節だ。つまり、中国人がオリンピックなどで優勝した時に流れる中国国歌は、「抗日映画」の一つ『風雲児女』(1935年)の主題歌なのである。
山東省出身の天亮は、個人的にはCCTVで一番好感が持てるキャスターだが、「抗日プロパガンダ」の片棒を担がされているのだ。
中国共産党政権にとって、「抗日戦争」とは、狭義では1937年7月7日の盧溝橋事件から1945年9月3日に勝利するまでの「八年戦争」で、広義では1931年9月18日の柳条湖事件から1945年9月3日までの「十五年戦争」を指す。
この番組の第1回放送を見ると、どうやら「7月7日から9月18日までを『抗日シーズン』とする」という着想のようだ。7月31日には、このシリーズの2回目「台児庄大戦」が放映された。
このような抗日キャンペーンは、習近平政権が発足した2013年から活発化したが、ここ数年は鳴りを潜めていた。それが2020年になって、戦後75周年とはいえ、再び頭を擡(もた)げてきたのである。
中国側から見た日清戦争
尖閣侵入、沖ノ鳥島調査、そして抗日キャンペーン……。日本にとっては何とも「穏やかでない夏」だ。これは一体、何を意味するのか?
私が思い起こすのは、4年前の夏の出来事である。
中国山東省の港湾都市・威海(Weihai)に、劉公島(Liugongdao)という一周約15kmの外島がある。威海の港から専用の船に乗って、15分ほどだ。そこは、清国時代に「海上の屏風」と称されて北洋艦隊の本部が置かれ、日清戦争(1894年~1895年)の最後の激戦地となった。
大日本帝国海軍は、何度も砲撃を加えたあげく、1895年2月に北洋艦隊を降伏させた。いまはその島の半分ほどを「中国甲午(日清)戦争博物館」にしている。中国で俗に言う「4大抗日博物館」の一角だ(他の3つは、ハルビンの侵華日軍第七三一部隊遺址、北京盧溝橋の中国人民抗日戦争紀念館、南京の侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館)。
4年前の夏、劉公島の広大な抗日博物館を訪れると、そこには「中国側から見た日清戦争」が詳細に展示されていた。
明治維新の6年後、1874年に日本軍が台湾に入ったことに驚愕した清国は、近代海軍の創設を決意した。1888年には、李鴻章(Li Hongzhang)北洋大臣が、劉公島に北洋艦隊を創設。「日本は文明の仮面をかぶりながら、野蛮な本性を露(あらわ)にした」と記されていた。
この博物館の展示によれば、日中が激突するきっかけとなったのは、1886年8月に起こった「長崎事件」だった。北洋艦隊の丁汝昌(Ding Ruchang)提督が軍艦「定遠」他を率いて長崎港に寄港した際、日本の警察と「定遠」の水兵たちが、激しい市街戦を起こした事件である。
日本では、中国人水兵たちが長崎市内で乱暴狼藉を尽くしたというのが定説になっている。だがこの博物館では、日本側に全面的に非があったと解説していた。
ともあれ丁提督は、この勢いで日本が軍拡していけば中国が大変なことになると、強い危機感を抱いて帰国した。そこで、西太后(Cixitaihou)が牛耳っていた北京の宮廷に、日本の脅威を伝える。
ところが西太后は、夏の離宮・頤和園(いわえん)増築のため、海軍予算をカットしようとしていたくらいで、取り合わない。周囲の重臣たちも、外敵の脅威よりも、いかに西太后に取り入るかに執心していた。
そうした中、日本は現地の在留邦人を保護するという名目で朝鮮半島に軍を派遣し、朝鮮の宗主国である清国と激突したのである。日の昇る若い明治日本と、落日の老いた清国とでは、勢いの差は歴然としており、陸戦でも海戦でも日本軍の連戦連勝だった。
かくして下関条約で、清国は日本に台湾と遼東半島を割譲し、2億両もの賠償金を支払うことになったのである。これが遠因となって、清国は1912年に滅亡してしまった。
展示室には、北海艦隊の25隻の主要艦船の模型などが、飾られていた。日中ともに次々と、欧米列強に艦船の製造を発注したが、結果は明暗を分けた。
日清戦争直前と現在の状況は瓜二つ
この博物館(陳列館)の入口には、近代中国の著名な思想家・梁啓超(Liang Qichao 1873年~1929年)の言葉「わが国の千年の大きな夢を喚起せよ。それは甲午(日清)戦争から実行するのだ」が掲げられていた。
梁啓超は、かつて横浜に住んだりもして、思想遍歴の激しい人物だが、毛沢東元主席がこよなく尊敬していた。思うに、毛沢東元主席を「政治の師」と仰ぐ習近平主席は、ここから「中国の夢」という自らの政権のスローガンを拝借したのではなかろうか。
習政権のスローガンは正確には、「中華民族の偉大なる復興という中国の夢の実現」である。つまり、「日清戦争以前の姿」に中国を戻すということだ。
博物館の出口には、「中国人民はいままさに、中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現すべく奮闘中であり、歴史から知恵を汲み取れ」という習近平主席の檄文が貼られていた。
こうして半日かけて劉公島を見学した後、私が一つ、歴史から汲み取ったことがあった。それは、日清戦争直前の状況と、現在の状況とが、瓜二つだということである。しかも、19世紀末の日中と、現在の日中とを、あべこべにすると、である。
具体的に19世紀末の状況は、ごく簡略化すると、以下のように整理できる。
《日本》
・富国強兵、殖産興業を合言葉に、軍事力と経済力を増強し、アジアの新興大国として台頭しつつあった。
・イギリスとの不平等条約を改正しようと躍起になっていた。
・一時的な経済悪化から、伊藤博文内閣は国民の目を外にそらしたかった。
《清国(中国)》
・日本の軍拡と挑発が恐ろしくて、欧米列強に調停や威嚇を依頼していた。
・最高権力者の西太后を中心とした北京の朝廷も、国民も、平和ボケしていた。
・丁汝昌提督ら軍幹部がいくら危機を訴えても、朝廷は専守防衛を命じるのみだった。
この比較から、何か気づかないだろうか。そう、日本と中国をひっくり返すと、現在の状況にピタリ当てはまるのだ。現状を整理してみると、以下のようになる。
《中国》
・習近平政権は強軍強国を合言葉に、軍事力と経済力を増強し、アジアの新興大国として台頭している。
・アメリカとの「新冷戦」(貿易戦争・技術戦争など)を打開しようと躍起になっている。
・冬の新型コロナウイルスと夏の記録的豪雨による経済悪化で、国民の目を外にそらしたい。
《日本》
・中国の軍拡と挑発が恐ろしくて、アメリカに防衛を頼っている。
・末期の安倍晋三長期政権も、国民も、平和ボケしている。
・海上保安庁や防衛省・自衛隊が危機を訴えても、安倍政権は専守防衛を命じるのみである。
この通り、日中の立場を入れ替えると、まさにピタリ一致するのである。
トゥキディデスの罠
となると現在、中国側が尖閣諸島近海で起こしている行為に対して、日本は悠然と構えていてよいのだろうか? このままでは、「第2次日清戦争」が勃発してしまうのではないだろうか?
前述のように、習近平主席自身が、「中国人民はいままさに、中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現すべく奮闘中であり、歴史から知恵を汲み取れ」と、意味深な言葉を吐いている。
私は1995年に、北京大学に留学したが、この年の入学生は全員、一連の入学行事の中で、『七七事変』という抗日戦争勝利50周年記念映画を観させられた。私も観たが、彼らは口々に「もう一度、日本と一戦交えたい」と言っていた。そんな彼らは、いまや習近平政権の中枢にいる。
国際政治学で、「トゥキディデスの罠(わな)」という言葉がある。
紀元前5世紀のギリシャのペロポネソス戦争を記述したアテネの歴史家トゥキディデスは、「アテネの台頭と、それが盟主スパルタに与えた恐怖が、戦争を不可避にした」と結論づけた。そこで、米ハーバード大学のグレアム・アリソン教授は、覇権国と挑戦国の深刻な対立のジレンマを、「トゥキディデスの罠」と名づけた。
実際、過去500年で覇権国と挑戦国の対立は16回起こっており、そのうち12回で戦争になったという(グレアム・アリソン著『米中戦争前夜』ダイヤモンド社、2017年)。
現在、世界で論争になっている「トゥキディデスの罠」は、覇権国のアメリカと挑戦国の中国の間の戦争は、不可避なのかどうかということだ。このコラムでも先月、詳述したように、すでに「米中新冷戦」という言葉も使われ始めている。
だが、考えてみれば、「トゥキディデスの罠」は、何も世界ナンバー1と世界ナンバー2の間の対立・対決のみに当てはまるものとは限らない。アジアのナンバー1とナンバー2の間の対立・対決にもまた、当てはまるのである。
日本が覚悟すべきこと
東アジアにおいては、古来、中国を中心とした文明圏が築かれてきた。ところが、1840年のアヘン戦争で清国がイギリスに敗れて以降、清国が徐々に傾いていく。
一方で、日本は古来、島国ということもあって、鎖国的意識が強かった。それが19世紀半ば以降、明治維新でほぼ無血革命を成功させ、欧米列強に並ぶアジアの新興国として、急速に発展を遂げていった。
こうして19世紀末に、東アジアにおいて、「トゥキディデスの罠」が起こった。その結果が日清戦争であり、東アジアの盟主は、中国から日本に入れ替わった。
続く20世紀は、前半は軍事的に、後半は経済的に、東アジアにおいて「日本の時代」が継続した。
だが21世紀に入って、再び中国が台頭してきた。一方の日本は、バブル経済崩壊以降、「失われた20年」と呼ばれる停滞の時代を迎える。そして少子高齢化が加速したこともあり、急速に国力を低下させていった。
こうした結果、2010年にGDP(経済力)で、ついに日中が逆転した。10年後の2020年は、3倍近くまで差がついている。軍事費でも、ストックホルム国際平和研究所の「2019年世界軍事費比較」によれば、中国は日本の約5.5倍まで来ている。
つまり、日中は確実に逆転しつつあり、そこに新たな「トゥキディデスの罠」が起こっているのである。その最前線が、尖閣諸島というわけだ。
となると、尖閣諸島をこのまま放置しておけば、近未来には当然、中国のものになってしまう。かつての日清戦争では、日本は巨大な台湾島を清国から割譲させたのだ。その脇に位置する小島(尖閣諸島)など、ひとたび合戦が始まれば、ひとたまりもないだろう。
そして、中国がここへ来るまで120年以上も要していることを鑑みれば、一度取られたらもう二度と戻らないと、覚悟しておくべきだろう。
近藤 大介(『週刊現代』特別編集委員)






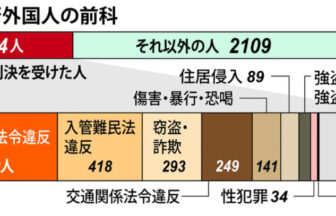


















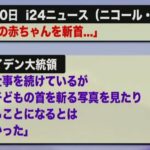
























この記事へのコメントはありません。