7/14(火) 7:01配信
韓国の衝撃…ここへきて韓国から「脱南」する脱北者たちが急増していた!
冷戦時代、脱北し韓国に渡ってくる人たちは「英雄」として扱われた。私が小学生だった1983年、MiG-19を操縦し脱北してきた北朝鮮軍上尉・李雄平氏のケースが代表的だ。
当時、北朝鮮の主力戦闘機であったMiG-19を持ち込んだということは相当に衝撃的だったが、現役軍人が命を懸けて脱出してきたというだけでも、熱烈な歓迎を受けるには十分だった。当時、私が購読していた小学生新聞に彼の脱出記が連載されていたことをよく覚えている。それだけ韓国を熱狂させたのだ。
休戦線を越えて南側にやってくる北朝鮮の軍人、民間人には韓国政府が住居や仕事を斡旋し、巨額の補償金を渡し韓国社会に定着するよう手厚い支援がなされた。
だが今、冷静に振り返ってみれば、それらは脱北者「個人」を尊重し、考えてのことではなかった。それらは北朝鮮と韓国が水面下で熾烈な競争を繰り広げていた冷戦時代に、韓国の優位性を宣伝する絶好の機会を作ってくれたことに対する「ご褒美」だったのである。
しかし、やがて『英雄』たちの身分は『凡人』へと変容する。90年代、即ち食糧難、「苦難の行軍」として知られる時代に脱北者の数が急増したためだ。
英雄は希少価値があったからこその英雄であって、誰もが簡単になれるなら、どこででも目にすることができるなら英雄としての価値はない。「英雄」としての存在感が薄れたのは当然の帰結だ。
それでも90年代末まで累積1000名に満たなかった脱北者の数は、2000年代に入り年間2000名へと急増、2019年に至り累計3万3千名を突破した。「脱北ラッシュ」とも言われるような時代が到来したのだ。
脱北者の数は増加し、彼らは韓国内に定着し多様な分野、職業に就くようになった。大学生、商業、公務員、労働者、芸能人、漫画家、記者といった一般的な職業に留まらず、今年の4月の総選挙では脱北者出身で初の国会議員2名が保守野党から誕生し大きな話題になった。
脱北者らは名実ともに韓国社会の一部を構成するようになったのだ。
だが、「脱北」という形で韓国に「不時着」した彼らすべてが、韓国社会に「ソフトランディング」したわけではない。韓国社会に適応できず、悩みとストレスを抱え、不満を抑えきれずにいる人々も少なからず存在している。
統一部傘下の公共機関である南北ハナ財団が作成した実態調査によると2019年現在において脱北者たちが挙げる最も大きな不満は家族と離れていること(27.6%)だ。これは不満というよりは悩みというべきもので北朝鮮にまだ家族が残っていたり、韓国に来ることができず第3国に足止めされている場合に、家族と会えないもどかしさ、あるいは悲しみが常に彼らを苦しめているという。
2番目は競争が余りにも熾烈だ(19.0%)ということだ。共産主義社会とはいっても競争が全くないわけではないだろうが、資本主義国家で収入や地位をめぐって勃発する命がけの生存競争は、彼らにとって想像を絶するほどの激しく、辛いものだということだ。
「義務」として行われる労働が「欲望」のために行われる労働に勝てるはずがないのは今や常識といってもいい。これまで経験したことのないような高度な競争社会に適応することは脱北者たちにとって高い障壁となっている。
3番目は脱北者に対する韓国社会の差別や偏見(15.4%)だ。
韓国は外国人がみたら驚くほど「民族」という言葉を強調する国だ。だがそれは、同じ民族の人を無条件に歓迎するということを意味するわけではない。同じ民族だとしても外国から来た人に対しては他民族の外国人に対するよりも冷たいのだ。その代表例が中国出身の朝鮮族や脱北者たちに対する態度だ。
彼らは韓国では外国人、あるいはそれ以下の扱いを受けるのだが、中でも最も底辺の扱いを受けているのが脱北者たちだ。脱北者たちが就職するときに「脱北者よりは就職しやすい」という理由で朝鮮族だと身分を偽るというケースもあるほどだ。
「脱南」する脱北者たち
このように、韓国社会に適応できない脱北者たちの中には、再び新しい生活の場を求めて『脱南』を試みる人たちもいる。脱北者たちが脱南する際の目的地はイギリス、カナダといった欧米諸国だ。難民に対する待遇がいいというのが大きな理由だという。
欧米諸国に渡ったからといってアジアからきた難民に対する偏見や差別が無いというわけではないだろうが、脱北した人たちは韓国で同じ民族から受ける差別よりは、欧米諸国で2等国民として生きる方がまだ諦めがつくという。受けるストレスの量が違うというのだ。
一方、多くの韓国人は彼らが「脱南」することを快く思わない。脱南者たちのうちの大部分は難民として認めてもらうため、脱北し一度は韓国に渡ったという事実を隠すか、あるいは、韓国内で差別をうけたということを大げさに強調するためだ。
韓国へ来た脱北者たちは一定期間、社会適応の為に教育と経済的支援を受ける。そして韓国社会に出て、血のにじむような努力と競争の末に経済的に自立し、成功を収めた人も少なくない。そういった人たちがいることを知っている韓国人の立場から見れば身分を偽ったり、韓国内での差別を強調して亡命しようとする脱北者たちは単なる「不適応者」にしか見えないのだ。
脱北者の立場も、彼らに対する韓国人の評価も、理解できないわけではない。より良い生活を求めて被害を強調する人たち、一方で税金でもって彼らを支援した人たちが感じるやるせなさ。同じような葛藤や意見対立は韓国だけでなく、いくつもの難民受け入れ国家において珍しくない光景だ。
だが、最近になってこれらとは全く異質なもう一つの「脱南の理由」が登場した。それは脱北者たちが韓国において感じる「命の危険」だ。
「脱北は罪だ」 …脱北者たちに北に帰れと言う人々
慰安婦支援団体をめぐる告発は韓国全土に衝撃を走らせた
慰安婦支援団体として知られている挺対協の前代表尹美香氏が今年4月15日に行われた総選挙において比例代表として国会議員に当選した。ところが今、彼女が代表を務めていた時期に資金流用をしたという疑惑が浮かび上がり世間を騒がせている。
中には慰安婦たちの休養施設として購入、維持されていた不動産の売買が含まれているのだが、この休養施設に関する情報をメディアが追跡する中、驚くべき証言が飛び出し、報道された。
2016年4月、北朝鮮が外貨を稼ぐために中国の浙江省で経営していた柳京食堂から、支配人許某氏と女性従業員12名が集団脱北し韓国に亡命するという事件が発生した。当時、北朝鮮側は朴槿惠政権の国家情報院が北朝鮮住民を拉致したと反発し、韓国側は自由意志による亡命だと反論した。
北朝鮮は北朝鮮にいる彼らの家族を動員し「拉致された従業員たちを返してくれ」と国連人権委員会へ訴えたが、人権委員会は従業員たちが自由意志を表明できる状況にあると北朝鮮の異議申し立てを棄却した。
「お前死ぬ準備をしとけ」と…
その後、彼らは他の脱北者同様、韓国内の施設で教育および適用期間を経て韓国社会に出た。一時、韓国社会を騒がせた彼らも、徐々に人々の記憶から忘れられていった。そんな彼らの存在に再び注目が集まったのは、慰安婦支援団体の不正疑惑の一つだった慰安婦のための休養施設に関する記事からだった。
柳京食堂の支配人だった許氏が2018年10月、ソウル市麻浦区にある慰安婦施設に招かれたのだが、その場で尹美香前代表、左翼系弁護士団体「民弁」の弁護士3名、朝鮮総連系の女性3名に「脱北は朴槿恵政権の国家情報院(以下、国情院)の企画によるものだった」と記者会見をするように懐柔されたと暴露したのだ。
許氏によると、彼がその計画に関心を示さずにいると、一か月後に再び慰安婦施設や山の中の山小屋に招待され、北朝鮮に帰るよう勧められ、それを断ると民弁の弁護士から「脱北は罪」だという衝撃的な言葉まで投げかけられたという。
やがて正体不明の人々が許氏の住む家までやってきて脅迫するような事態にまで発生した。許氏の通報で出動した警察が脅迫犯を捕まえてみると、犯人2人はいずれも女性で1人は中国出身の朝鮮族、もう一人は韓国系日本人だった。彼女らは許氏に対し「国情院の手先め、お前死ぬ準備をしとけ」といった暴言を吐いた。
許氏は住民番号や名前を2回も変えて生活していた。しかし、それでも居住地がバレたことに大きな精神的な衝撃を受けたに違いない。許氏は彼女らが自分の居住地を確認しに来た「暗殺先発隊」だと感じ、統一部や国情院に居住地の変更を要請したが、十分な処置はしてもらえず、命が保障されないことを感じた彼は結局2019年3月韓国を離れ海外に亡命した。
通常、脱北者が再び海外に亡命するのは難しいが、亡命先の政府は彼が韓国で迫害され、危険にさらされているという事実を認めたのだ。
文在寅政権が親北に傾くにつれて…
韓国で脱北者たちが政治的受難に巻き込まれる事例は以前にもあった。
2013年親北左派の野党議員が脱北者に対し「大韓民国にきたら口を噤んで、静かにしてろ、裏切り者のガキども。お前、身辺に気をつけろ」という暴言を吐いた事件は象徴的だ。
当時は北朝鮮との関係が良くなかった李明博政権下であったにもかかわらず、親北勢力の少なくない韓国で脱北者たちは、このような扱いを受けていた。ましてや現在は当時よりもはるかに親北に傾いた政権だ。脱北者たちの心情はいかばかりか。現政権が北朝鮮に振り回され続ける限り、韓国内にいる彼らの不安が消えることはないだろう。
脱北者たちは韓国はもはや魅力的な避難地ではないと感じているかもしれない。
それを大げさだと思う人もいるだろうけど、「命」がかかっている彼らのその本能的な感覚は、高い政権支持率や政権万歳の報道に酔っている韓国人たちの感覚より、はるかにリアルな実情を反映しているのではないだろうか。
崔 碩栄(文筆家)

























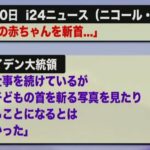
























この記事へのコメントはありません。