「アフターコロナには現金がゴミになる」金価格が高騰する根本原因
プレジデントオンライン
■政府・中央銀行の野放図な資金供給で歪む世界
金価格が高騰を続けている。7月1日には一時1788.96ドルまで上昇し、2012年10月以来の高値を付けた。と思ったら、7月9日にはさらに1820.60ドルまで上昇してきた。
そして、7月22日のアジア市場では日本時間9時30分の時点で1847.29ドルまで急騰している。いよいよ2011年9月につけた史上最高値の1920.30ドルが視野に入ってきた。
ポートフォリオに金を加えるべきだ、というのが私の考えだが、金を買うべきか、そろそろピークと考えるべきか、読者のみなさんが自分で見極めるためには、投資商品としての金を単体で見るのではなく、世界経済の大きな動きを読むべきであろう。以下説明していこう。
全世界で感染者が1470万人を超えた(7/21現在)新型コロナウイルスの感染拡大で、一時的にせよ、各国が経済活動を完全に止め、大量の失業者が発生している。各国企業は収入を絶たれ、債務不履行・倒産のリスクが高まっている。
主要国の政府・中央銀行は矢継ぎ早に対策を打ち出し、大量の資金投入を行うことにコミットした。その結果、2020年2月以降に大きく下落していた株価は、早くも3月には底打ちし、持ち直しの動きが強まるなど、株価だけを見れば経済的な不透明感が払拭されたかのような雰囲気が一部である。
だが、今回打ち出された野放図な資金供給という政策が、はたして将来にわたって継続することは可能なのだろうか。また、副作用はないのか。
■リーマン・ショック時の中国と同じ過ち……
莫大な資金供給で経済を無理やり回復させたのが、2008年のリーマン・ショック時の中国の巨額の財政出動だった。しかし、このような政策は、表面上はうまくいっているようでも、経済の実態とは大きな乖離が生じる。結局は需要のないところに無理やり資金を供給してさまざまなものを生産し、供給することで、経済が拡大しているかのように見せかけているだけでしかないからだ。
巨額の財政出動を受けて、実体のある十分な需要がついてくれば問題ない。だが、残念ながら得てして供給過剰に陥ってしまう。リーマン・ショック後の巨額の資金供給もご多分に洩もれず、「むしろ弊害が多かった」というのが後年の一般的な評価である。
当時、4兆元(当時のレートで約57兆円)にもおよぶ中国の巨額の財政出動で救われたのが欧米諸国だったが、その弊害が浮き彫りになり、今度はそれを批判し始めた。ところが現在、当時の中国とまったく同じことをしている。中国を批判する資格がないどころか、今後、世界経済に多大な悪影響を与えるのではないかと心配せざるを得ない状況だ。
■金融商品の焦げ付きという「新たなパンデミック」
世界の経済成長率は大きく落ち込み、短期間では戻らない。世界的に経済活動が再開されても、以前の規模に回復するには数年単位の期間が必要とみられる。
これまで米国などでは、株主還元の名のもとに、さんざん借金をして自社株買いを行い、配当を増やして株価を上昇させてきた。その状況を作り出したのちに、経営者は保有する自社株を高値で売り抜け、経営から退き、借金も放り出してきたのである。あとを受けた経営者からすれば、たまったものではない。
そこで起きたのが新型コロナウイルスの感染拡大であった。経営者たちは経営が苦しくなり、中央銀行に駆け込んで「債務を引き受けてほしい」と迫っているというのが現状である。
2008年のリーマン・ショックのときもそうだ。金融機関がサブプライムローンを束ねた金融商品(デリバティブ)を世界中にばらまき、それが焦げ付いたことで金融危機が発生。最終的にリーマン・ブラザーズという当時の投資銀行が破綻し、世界的な金融危機を引き起こした。
まさに、金融商品の焦げ付きが「パンデミック」となり、世界の金融市場だけでなく、経済にも大きな悪影響を与えたわけだが、世界を震撼させ、経済を大きな落ち込みに陥れた金融機関の経営者にはほとんど何も負担がなかった。
■「不良債権のゴミ箱」化するFRB
新型コロナウイルスの感染拡大という背景があるにしても、企業は資金不足を理由に多額の社債を発行している。米企業の2020年4月の発行額は総額2294億ドルと、前年の3.6倍となり、月間ベースで過去最高を記録した。米連邦準備制度理事会(FRB)が大規模な社債購入を決めたことが、投資家の需要の回復につながったようである。
新型コロナウイルスの感染拡大で経営が著しく悪化している米ボーイングも社債を発行したが、その上乗せ金利は4.5%。2019年7月の発行分の0.9%から大きく上昇した。また、業績不振で政府に支援を仰いだデルタ航空も起債し、当面の資金繰りにめどを付けたものの、年7%の高い利回りが設定された。
このような高利回りに投資家が飛びつき、結果、ハイイールド債への需要が高まった。FRBが総額7500億ドルの買い入れ枠を設定したことで、FRBが「最後の買い手」として控えている安心感が起債の急回復につながったのであろう。
企業が債務不履行になっても、FRBが債務を肩代わりしてくれるのであれば、投資家には何もリスクがないことになる。まさに「フリーランチ」であり、「やった者勝ち」の経済だ。FRBがフリーランチの「ゴミ箱」になって、どのような不良債権も買い上げることができるというのであれば、これはもう「モラルハザード経済」といってもいい。
冷静に考えればわかるように、このような仕組みはいずれ破綻する。
■「フリーランチ」は存在しない
FRBの使命は「雇用の最大化」と「インフレ率の抑制」だ。債券の買い入れによる経済の安定化ではないことは言わずもがなである。したがって、FRBが今回採用した政策への批判が高まるのは必至であり、FRBも買い入れる社債を選別せざるを得なくなる。
そのとき、結果的に企業債務が拡大し、債務不履行による倒産ラッシュが起きることになる。多くの投資家が、不良債権をFRBがすべて引き受けるのは不可能であると思い知らされることになるのだが、そんなことは初めからわかり切っている。
そのとき投資家は「FRBが社債を買うと言ったじゃないか」と批判するだろう。しかし、そもそもフリーランチは存在しない。投資家が無知だったということになるだけだ。
■「現金がゴミになる」
経営者や金融機関、投資家だけがさんざん儲けておいて、その後のツケを国民が引き受けるというバカげたことはあってはならない。金融機関や大手企業は、「政府に守られていると考えるのは、最終的に大きな勘違いだった」と思い知らされるタイミングが来るだろう。
今後の低成長時代に、実体経済や企業の実力に見合わないような株価水準に上がることもなくなっていく。資金供給の拡大で、株価が人為的に押し上げられるような経済が、永遠に続くと考えるには無理がある。
さらには、政府・中銀による野放図な資金供給が行われることで、今後は通貨が下落する可能性がある。いや、もっとはっきり言えば、「現金がゴミになる」という世界が来るかもしれない。デジタル化の加速で、そのような状況がいずれ鮮明になっていくだろう。
米ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で2020年4月20日、国際的な原油取引の指標WTIの5月の先物価格が1バレルあたりマイナス37.63ドルと、史上初めてマイナスを記録した。原油価格がマイナスになるという“考えられないこと”が起こったのである。これからは何があっても驚いてはならない。
人口動態の問題も、今後は重要なポイントになる。少子高齢化は経済の縮小均衡を意味する。「人・モノ・カネ」の流れが止まれば、デフレになる。現金が力を持つ世界になるということでもあるから、デフレであるうちはまだましかもしれない。しかし、その現金の価値が、デジタル化の加速の中で低下していったとしたらどうか。
■「架空経済」の崩壊
2021年に東京五輪・パラリンピックが本当に開催されるかはまだ誰にもわからない。その先の世界経済の動向はもっと不透明な状況だ。
ただ言えるのは、新型コロナウイルスは、これまで中央銀行による資金供給で支えられてきた「架空経済」の崩壊をもたらすことになるということだ。
2021年以降は10年間ほど、厳しい状況が続くかもしれない。これまで十数年間、米国を中心にバブル経済に踊りに踊ってきたわけだから、それくらいの厳しい状況は我慢しなければならない。世界的な停滞が長期間続くリスクを念頭に置くことが求められている。
ちなみに、1929年の米国に始まる世界恐慌の際には、株式市場の回復に約25年かかっている。今回はさすがにそのような長期間にわたることはないだろうが、それくらいの長期的視点と覚悟をもって日々の生活を過ごしていくことが求められるだろう。
■ジョージ・ソロスの教え
私が投機家としてもっとも尊敬するジョージ・ソロス氏は、新型コロナウイルスのパンデミックとその影響について、「資本主義の未来にとって何が起きるかわからない、かつてない出来事」としたうえで、「私たちはパンデミックが始まったころの状態に戻ることはない。それは明らかだ」と述べている。
確かにこれだけインパクトのある出来事は、人生でそう多くはない。ワクチン開発が成功するまでにも長い時間が必要になるだろう。米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)の所長で、トランプ政権の新型コロナウイルス対策本部の主要メンバーでもあるアンソニー・ファウチ博士は、「年内にウイルスが根絶される可能性はほぼない」としている。私たちには、新型コロナウイルスと共存していく覚悟が必要だ。
今回、これから世界に起こりうる基軸通貨ドルの価値の減価、米国株バブル経済の崩壊状況と、歴史的な世界の覇権国家の移行可能性を分析し、新著『金を買え 米国株バブル経済終わりの始まり』(小社刊)を上梓した。
金が今後1トロイオンス=2000ドルを超えて上昇する可能性とその理由についても詳しく考察している。「金を買え」といっても、資産運用の話にとどまらない。見えない未来、見えない社会の先を読み、自分自身の資産ポートフォリオを再構築し、新しい時代を生き抜いてほしいという願いを込めている。
※本稿は、江守哲『金を買え 米国株バブル経済終わりの始まり』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
江守 哲(えもり・てつ)
エモリキャピタルマネジメント株式会社代表取締役
慶應義塾大学商学部卒業後、住友商事に入社し、非鉄金属取引に従事。1996年に英国住友商事(現欧州住友商事)に出向しロンドンに駐在。その後、Metallgesellschaft Ltd.、三井物産フューチャーズを経て、2007年7月にアストマックス入社。同社でファンドマネージャーに就任。アストマックス退社後、2015年4月にエモリキャピタルマネジメントを設立。ヘッジファンドを中心とした資産運用や株式・為替・債券・コモディティ市場の情報提供などを事業として展開。
エモリキャピタルマネジメント株式会社代表取締役 江守 哲







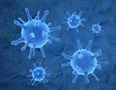
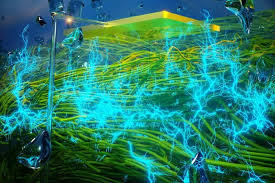







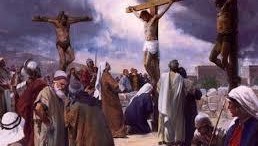

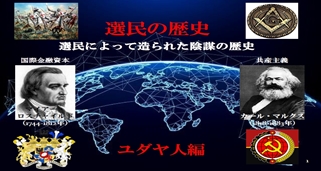
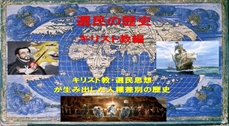
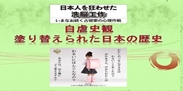




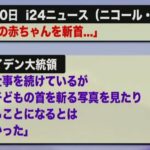
























この記事へのコメントはありません。