(塚田 俊三:立命館アジア太平洋大学客員教授)
新型パンデミックは、未曽有の影響を世界経済に与えた。もはやV型復活は期待できず、長期にわたる、L字型の回復となるであろう。各国の財政金融当局は、コロナショックを和らげるために必要なすべての対策を採るとし、米国は、3月、コロナ対策として、2.2兆ドルの緊急経済対策を採決し、EUも7月下旬に7500億ユーロの緊急支援を決めた。
我が国においても、32兆円のコロナ対応型の第二次補正予算を組み、102兆円の2020年度一般会計予算に上乗せするとした。国債依存度は、戦後初めて5割を超え、56%に達する。だが、その資金はどこから出てくるのか。税収からではない。すべて、特例国債、即ち、赤字国債からである。
このような歯止め無き財政支出の拡大、そのための、国債の大量発行は果たして許されるものであろうか。もはや、基礎的財政収支均衡の2025年までの達成は夢のまた夢となってしまった。それでも、市場では意外にも楽観的な見方が強く、いまの国債金利は10年物ですら0.05%と、ほぼゼロに近く、将来の金利負担は軽い。心配無用とする。だが、問題は、10年後の国債借換え期における金利水準がどうなっているかであり、それが高騰していれば、国債は雪だるま式に増えていく。
我が国の公的債務は積りに積り、国の普通国債残高だけで、令和2年度末までには906兆円、GDPの実に151%に達するといわれている。累積債務もここまでくれば、財政破綻の臨界点に限りなく近づいているといえよう。これ以上の国家債務の増大は何としても食い止めなければならないし、それだけではなく、その大幅削減を図らなければならない。だが、果たしてその方策はあるか? 無くはない。全額解消は難しいとしても、その半分の解消は可能である。次の3段階方式によれば、である。
■ 第一弾:国庫債務と日銀債権の同時相殺
現在、国が発行した国債の43%は日銀が保有する。先ずこの日銀保有分の国債に係る債務を解消できないかという点である。次の図を見て頂きたい。左側は、国庫の貸借対称表、右側は日銀の貸借対照表である。
ここで提案したいのは、近い将来のある時点で、国が日銀に対して有する債務と、日銀が国に対して有する資産(国債)とを同時に相殺してはどうかということである。債権者と借り手が合対立する一般の金融取引であれば、資産と債務の相殺は難しいが、それが、政府内の二つの分身の間においてであれば、相殺は可能である。しかもその操作は極めて簡単であり、日銀内にある国庫の貸借対照表と日銀の自己勘定としての貸借対照表との間の帳簿の操作として処理としうる。
だが、もしもかかる措置が採られれば、現行体制の大幅な変更を伴うではないかという懸念が生まれる。
その心配はいらない。
この相殺後も(以後ビッグバンと仮に呼ぶ)、日銀の業務は以前と変わらず、日銀は、従来通り、日銀券の発行管理を行い、金融政策を司り、市中銀行、地銀等の監視・考査業務、更には、金融機関同士の決済の扶助も行う。
確かにビッグバン後は、日銀の預かり金としての“政府預金”は消えるが、日銀は引き続き国庫の管理業務を行う。ただ、それは、従来のような顧客から預かった資金の管理ではなく、国庫の管理“委託事業”としてである。日銀は、大正11年までは、国庫の管理を大蔵省からの委託事業として行っていたが(「委託金庫制度」)、それと同じ仕組みに戻るだけのことである。
勿論国庫も従来通り存続するが、ビッグバン以降はその管理責任者が財務大臣であることがより明確となる一方、その事務はすべて日銀に委託される。
だが、ここでいうような累積債務の半減といった大胆な施策を、二つの勘定間の操作といった簡単な措置だけで行っていいものであろうか。それが正当な手続きの下で行われる限り是とされる。
金融界では、“無から有を生み出し”、あるいは、“有を無に変える”ことは、決して稀なことではない。その端的な事例が、IMFが1969年に創出したSDR(特別引出権)である。それは全くの“無”から、米国にとっては金に相当する外貨準備資産を、他のIMF加盟国にとってはドルに相当する外貨準備資産を純然たる帳簿の操作によって生み出したものである(詳細については別稿で述べる)。
また、金融商品としてのデリバティブも“無から有を生み出した”事例であるといえよう。したがって、現在、国庫の“最終的かつ総括的な現金出納機関”として指定されている日銀が、その内部に設置された国庫の貸借対照表と日銀の自己勘定としての貸借対照表との間で同時相殺することは、何ら問題ない。要は、時の政権の決断次第である。
■ 第二弾:政府通貨の発行
上記の措置により政府はその累積債務の半分近くを減らすことができるが、ここで注意を要するのは、このビッグバン後も政府がその支出を従来通り日銀券で行えば、再び政府債務は増え始める。
この悪循環を断ち切るためには、政府は、ビッグバン以降は、その支出はすべて政府通貨で行うとの大転換に踏み切ることが必要である。というのは、政府が、その支払を日銀券で行えば、国の債務となるが、これを政府紙幣で行なえば、国の債務とはならないからである。
どうしてそのような違いが出てくるのかという疑問が生じるかもしれないので、ここで簡単に日銀券発行のメカニズムに触れる。
現在、国庫の収入、支出は、すべて日銀に設定されている“政府預金”から行われているが、政府の支出が税収を超える場合は、政府は国債を発行して必要資金を調達せざるを得ない。
国債の売り上げはすべて政府預金に入金されるが、政府からの追加入金分は、日銀の目から見れば、資産の増大であり、日銀は、複式簿記の原則からこの資産の増加に見合う分だけ、負債を増加させる必要があり、この負債の増加は日銀券の増発という形で行われる。
別の言い方をすれば、増発された日銀券は、国債の増発に支えられているものであり、その国債は、国の債務であることから、上記の違いが出てくる。
ここで、政府通貨の発行というとかなり唐突な提案に見えるかもしれないが、本来政府は、通貨発行権を有しており、この権利を直接的に行使すると、その形態は政府通貨となり、これを間接的に中央銀行を通じて行使すると、銀行券となる。
歴史的にも、明治以降、大正、昭和を通じ、政府は何回も政府紙幣を発行してきており、平成に入ってからも財務省内で真剣にその発行が検討されたことがある(2004年に竹中平蔵大臣の下で、2008年には渡辺喜美大臣の下で、2009年には麻生太郎首相の下で)。
米国においてもオバマ政権時代に、議会が政府の借入限度額の引き上げをなかなか了承しなかったので、しびれを切らしたオバマ政権は、最後の手段として1兆ドルのプラティナム・コインの発行を検討したことがある(2013年)。これは、コインであれば連邦政府が発行し、通常のドル紙幣のように連銀が発行するものではないので、連邦政府の債務とはならないからである。
■ 第三弾:デジタル通貨としての政府通貨発行
ここで上乗提案をしたいのが、上記の政府通貨の発行を「デジタル通貨」として発行することである。政府通貨の発行は、これを担保する何らの資産の裏付けも必要とせず、デジタル通貨の性格により適合するからである。
ただ、このデジタル政府通貨が新しく発行されると、従来から流通している日銀券との間で二本立てとなり、両者の間に価値の差が出て、流通市場での混乱を招くのではとの懸念が生まれる。この点については、ここで提案するデジタル政府通貨はあくまでも日銀券に対する補助通貨であり、その価値は日銀券にペッグされる。したがって、このデジタル通貨が発行されても通貨制度は二本立てとはならない。
デジタル通貨の発行については、政府も関心を有しており、この7月17日に打ち出した“骨太方針”のなかで、デジタル通貨の発行可能性に初めて言及し、デジタル通貨については “技術的な検証を狙いとした実証実験を行う”とした。これを受けて、日銀は本年2月来行ってきた研究を格上げし、審議役をヘッドとする重量級の“デジタル通貨グループ”を7月20日に立ち上げた。
ただ、日銀内で現在検討されているデジタル通貨は、日本銀行が発行するデジタル通貨であり、政府通貨としてのデジタル通貨ではない。しかし、技術面では、両者は大きく異ならず、そこでの検討は、政府デジタル通貨にも十分応用可能である。現在の検討の方向をあまり変えたくないということであれば、日本銀行デジタル通貨は当初予定通り発行することとする一方、政府支出に関わる分にだけ、政府のデジタル通貨を発行することとするのも一法であろう。
■ 終わりに
以上、日銀券に対する補助通貨としての政府デジタル通貨の発行を提案したが、いったん、これを認めると政府支出の限りない拡大と政府紙幣の乱発を招く恐れがあり、これを防止するためにこそ、現在の中央銀行券による通貨制度が生み出されたのであり、このような提案は慎重に行うべきであるとする批判が出てくると思われる。
だが、世界各国が現在採用している中央銀行券を主体とした通貨制度は、決して普遍的な制度ではなく、17世紀末に生まれたものにすぎない。それは、17世紀末、信用力が失墜した当時の英国ウイリアム3世政権の戦時資金調達を容易にするために編み出された制度に由来する。
具体的には、個々の債権者が寄り集まり、the Governor and Company of the Bank of England(英国銀行)と呼ぶ債権者集団を設立し、そこに金塊を持ち寄り、英国銀行の信用力を高めた上で、そこから、政府が発行する国債と引き換えに、銀行券を政府に発行するという仕組みであった。その際、英国銀行は、政府の全ての収入と支出を自己の管理下に置き、これによって政府に勝手な支出をさせないようにするとともに、金利、元本の確実な返済を確保した。これは、会社更生を図る際、管財人が更生会社の全財産を自己の管理下に置くのと類似した仕組みである。
以来この方式が、政府の放漫財政を妨ぐ上で有効であったことから、各国の通貨制度の基本として定着していった。このように現在の通貨制度を歴史的観点から見てくると、これを絶対視する必要がないことが分かる。
しかも、この制度は、当時のように金本位体制の下では有効であったかもしれないが、現在のように通貨制度がフィアット制(通貨の財サービスとの交換性が、貴金属の価値によって担保されるのではなく、政府の命令によって担保される制度)に替わってしまった今となっては、その有効性は薄れてきている。経済のすべての分野でデジタル化が急速に進む中、現在の通貨制度も新たな観点から見直すべき時期に差し掛かってきているといえよう。
塚田 俊三






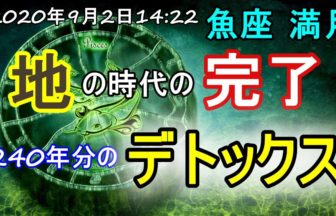









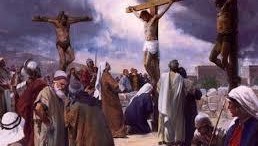

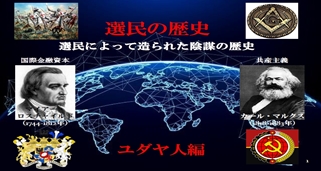
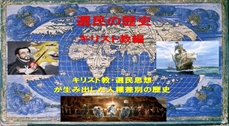
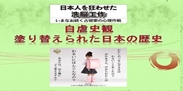




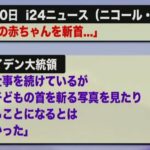
























この記事へのコメントはありません。