新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大、パンデミックの中で行われた韓国の総選挙で、与党が大勝した。
選挙運動が著しく制限され感染症対処だけが国民的課題になり、団結が大切と訴えた与党に有利に働いたからである。
その結果、文在寅政権は当面レームダックすることなく政策を進めていくことができる。
いや推進して親日勢力を弱体化し政権の安定を図らなければ、次期大統領選で敗北となれば報復の刑務所行きとなりかねない。それ以前に自身の夢が実現できない。
そこで、大勝を背景に現政権は理非を問わず、韓国の自由民主主義を潰す「極悪2法案」、すなわち連動型比例制への選挙法改正と、「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」新設法を成立させようとするに違いない。
対日関係では徴用工問題の推進である。韓国が「戦犯企業」に列挙した企業は270余社に上っている。
すでに三菱重工業や新日鉄住金をはじめ、不二越、横浜ゴム、住友石炭鉱業、日立造船などが提訴され、最高裁の確定判決が一部には出ている。
また、今年(2020)1月には川崎重工業や西松建設など6社が光州地裁に提訴された。
徴用工は本当に奴隷のように酷使され、また賃金で差別されていたのだろうか。
答えは『反日民族主義』で、落星台経済研究所の李宇衍(イ・ウヨン)研究員が日本の痩せこけた労働者の写真を徴用工のものと誤用していることを指摘した上で、「歴史の実体と複雑性は、反日種族主義に陥った研究者には想像もできない、より率直に申し上げると、彼らの知識の外のことです」と述べ、事実の追求を放擲してただ「反日」目的の捏造であると指摘している。
なお、1939年9月以降に半島から日本に来た人は「募集」で、1942年2月以降は「官斡旋」で、どちらも自由意志の来日であった。
1944年9月~45年4月の約8か月間だけが強制性を伴う「徴用」である。70万人中の約10万人とみられている。
本論では徴用が特定されている場合は「徴用工」と称するが、特定しない場合は「労務者」と呼称する。
[JBpressの今日の記事(トップページ)へ]
中島飛行機の概況
筆者は他用で中島飛行機(以下、「中島」と略称)を少し調べた。そこに徴用工についての記述があったので採り上げたい。
ただ中島を知らない人が多いと思われるので、西まさる著『中島飛行機の終戦』を主として参考にしながら簡単な概要説明から始める。
中島飛行機は海軍機関学校を卒業して技術将校として海軍機関大尉になっていた中島知久平が1917(大正6)年に創った会社で、知久平ほか8人でのスタートであった。
知久平は裕福な農家の長男に生まれた。父から所望された家業を継がずに海軍機関学校15期生として入校する。ライト兄弟が世界初の飛行を行った1903(明治36)年のことである。
1910(明治43)年にロンドンで開催された日英博覧会に花を添える目的で巡洋艦「生駒」が派遣され、知久平は派遣団の一員に選ばれる。
しかし、フランスの航空機を視察する計画を勝手に立て、なんとか上司の許可を得てマルセイユで下船する。
1912(明治45)年には航空機の整備と製作技術を習得するため4か月間米国に派遣される。その時も勝手に操縦技術を学び、操縦免許まで取得した。
家業を継がずに機関学校への進学に始まり、士官になった後のロンドン派遣や米国研修で見るように、知久平は思ったことを一途にやる大胆な性格があり、言うなれば異端児、良く言えば先見性の持ち主であった。
大艦巨砲主義の海軍にあって、「飛行機」の時代を主張する知久平は受け入れられず、海軍を飛び出し、航空機の世界に乗り出し、貧弱な態勢に似合わず、東京帝国大学から工学部航空学科の卒業生を破格の待遇で迎え設計部に投入する。
「組織の三菱」に対して「技術・人の中島」を目指したもので、のちのロケットの権威となる糸川英夫氏も中島に就職している。
「HⅡロケット」の萌芽も実にここに発している。
中島は「栄」、「誉」などのエンジンを生み出し、ゼロ戦のエンジンも中島製の「栄」であった。
1941年から45年までの戦争中に日本全体で製造した機体は7万機弱、エンジンは11万6577基で、中島が作った機体は2万機弱(三菱重工は1万3000、川崎重工は8000機)、エンジンは3万6440基に上り、実に3割を中島が作ったことになる。
ちなみに、真珠湾攻撃に参加したのは中島飛行機製の九七式艦上攻撃機と、零式艦上戦闘機(通称「ゼロ戦」、三菱重工設計、中島製)、九九式艦上爆撃機(愛知時計電機製)の3機種であった。
幻に終わった重爆撃機「富岳」
真珠湾における初戦の戦果に酔いしれていた日本であったが、米国の工業力が日本の比でないことを知り尽くしていた知久平(当時衆院議員で一派閥の長)は、この年に『必勝戦索』と題した論文を書き、政財界に配布したという。
そこには超大型戦略爆撃機「富嶽」の構想が描かれていた。
日本は長期戦には堪え得ないので、米本土にいきなり爆弾を投下し、敵を驚かせ戦意を喪失させて一気に和平に持ち込む、日本の生きる道はこれ以外にないという知久平の意志から生まれたものであった。
概略の性能諸言は全長36メートル、全幅55メートル、5000馬力エンジン6基搭載で、航続距離1万5000キロ、爆弾搭載量20トンで、B-29(全長30メートル、全幅43メートル、エンジン2500馬力4基、航続距離8000キロ、爆弾搭載9トン)をはるかに凌ぐ設計であった。
近衛文麿元首相や東條英機首相も支持して、三鷹製作所(東京)には「富嶽」用工場も造られ、知久平を委員長にした陸海軍協力の「富嶽委員会」も設置され実現の段階に入っていたという。
日露戦争の日本海海戦で東郷平八郎が「Z旗」を旗艦「三笠」に掲げて、「皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ」に因んだのであろうが、中島では運命を決する「日本最後の飛行機」という意味で「Z機」と呼んでいる。
群馬県太田市で太田製作所として始まった中島飛行機であったが戦時の生産をまかなえず、隣接して小泉製作所(昭和15年)、半田製作所(愛知県、同17年)、大宮製作所(埼玉県、同18年)、宇都宮製作所(栃木県、同19年)、浜松製作所(静岡県、同)など、次々に拡張し、戦争終結時の従業員は25万人であった。
敗戦(昭和20年8月15日)の2日後には民需産業への転換を意識して「富士産業株式会社」(富士重工業の前身)と社名を変更した。「富嶽」に由来していたことは言うまでもない。
創業から28年を迎えた中島は敗戦とともに、米国(GHQ)の専門家によって多方面からチェックされ、設計図をはじめ工具や製造マニュアルまで押収され徹底的に解体される。
ジェット機を試作、試験飛行まで行うなど中島に技術の大半が集中していたし、日本の軍用機の設計・開発からエンジンの製造、機体の組立てまで一貫して自社生産できる企業だったからである。
半田製作所の徴用工
半田製作所(愛知県半田市)には2万6000人の従業員がおり、これは中島飛行機全体のほぼ1割で、半島出身の労務者が数千人いた。
なお、西まさる氏は徴用工と書いているところが多いが、筆者が引用以外は労務者とした、以下同じ。
同製作所の副所長兼製造部長で実質的な最高責任者であった藤森正巳が残した「中島ノート」の戦争終結前日8月14日欄には、「学徒、挺身隊、應徴士ハ速カニ帰還セシム 採用ハ停止 女子ヲ先ニカヘス 半島労務者ノ処理ハヨク警察当局ト協議ノ上 成ルベク速カニ帰還方善処サレタシ 帰還旅費支給差支ヘナシ」などと記されている。
中島飛行機は敗戦4か月前に「第一軍需工廠」という国営の看板に替わるが、中島一族が経営する飛行機製造会社に変わりはなかった。
従って、「工場も機材も金も、すべて中島のもの、国のものではない」と認識していたが、占領後は誰のものとなるか分からない。
そこで、8月15日、会社は従業員に対する感謝の気持ちもあって全工員に、「自分が使っていた工具に限り、スパナやドライバー程度は持ち帰ってよい」と内々に通達したという。
ところが、自分が使っていた工具どころか、会社の時計や自転車、スクーターまで持ち出して帰るものが出て収拾がつかなくなる。
翌16日になると、朝鮮人労務者の乱暴者が工場内で物品の取り合いで暴れたり、大型機械からモーターを取り外して持ち去ろうとしたりして大もめにもめたという。
会社の好意が無になったわけで、即座に「工具持ち帰り許可」を取り消すが、簡単には収まらず、3日目のノートは「時々刻々変化スルカラ 持出 泥棒等ヲ厳ニスルコト 治安維持 火災 破壊 泥棒 風紀 警察 憲兵トヨク連絡」と書き、続けて「半島工員ニ対シテ ナルベク早クカヘスモ 帰路ノ途ガツカヌノニ、旅費ダケヤッテモ ダメナルニツキ方法ヲ講ズルコト」とある。
実際、一夜にして所を変え、戦勝国になった朝鮮人は東京、大阪などの大都市では土地を占拠して不法な行動を起こしていた。
西氏は「徒党を組み愚連隊化して乱暴を重ねる。そんなことが日常化していた」と書いている。もっとも、これは8月15日以降のことである。
朝鮮人の親方がすべてを仕切っていた
半田製作所には2000人から4000人の労務者がいたとされる。学徒は病欠1人まで副所長のノートにあるが、前月の労務者は1600余人、翌月は3800余人とあり、項目も「徴用工」や「一般工員」、「半島應徴士」など様々で、應徴士の人数欄は空白が再々あるが出金欄には出金が記載されているという。
藤森副所長にも半島からの労務者の区分が煩雑で、見えにくかったのかもしれない。
半田製作所では労務者の募集や管理監督を外部に委託していたため、乱暴する者などはおらず比較的平穏であったという。それどころか、労務者の方が日本の社員たちよりも生活にゆとりがあったことが以下の記述で伺える。
まずは、労務者の雇用環境と生活・労働の実態を知る必要がある。
募集業者が半島で集めた彼らは、日本に送られ、半田に来ると、地区を束ねる親方の傘下に入る。一種の組である。そして中島が用意した宿舎に入り親方の指示に従って製作所に働きに出る。
中島は組と契約を結び、個々の労働者に対して作業内容の指示はするが、労働条件には言及しない。
労務者はおおむね30人がグループになって出勤し、各グループには隊長や班長と呼ばれるリーダーがおり、彼だけが日本語が達者で部下に指示できるシステムで、中島の社員は作業指示も注意もリーダー任せという状況である。
「彩雲」組立工場には幾つかの労務者グループいて、作業が遅れているため工場長(日本人)がリーダーに「工員に残業させてくれ。2時間残業なら手当の他に食券を2枚付ける。4時間してくれたら全員に4枚付ける」と頼んだという。
当時は食糧難で、若い日本人工員や学徒は「残業は辛いが、嬉しい。食券が出るからやりたかった」といって、寮に帰っても食えるのを「アゲイン」と称して自慢さえした好条件であった。
工場長は必殺技と思って朝鮮人グループに頼むが、「いらん」といってすべて断られたという。
その理由を西氏は二つの驚きとして書いている。一つは、元海軍大尉で長身大柄で威厳がありなめられるような人物ではなかった工場長の業務命令を朝鮮人労働者が一瞥もなく拒否したこと。
叩かれたり強制されることはなく、話を重んじ、決して奴隷などではなかった証拠である。
二つ目は食券を欲しがらなかったことである。
朝鮮人が食券を欲しがらなかったのは、彼らの宿舎には食うに困らないだけのコメや肉、キムチがあり、ドブロクさえあって、食券に魅力を感じなかったからである。
当時の中島が管理したのは工場の出勤簿だけで、半島からの就労者の面接や管理、すなわち実数把握はしないで伝票どうりの人数を受け入れ、衣糧を払い出したという。
600人のところを親方が800人と誤魔化すこともできたようで、某製作所でこのカラクリが発覚したという。
ある地区の労務者のまとめ役だった親方(日本名を使用していた)は寮でなく民家で暮らし、時々寮を見回り、中島飛行機と交渉するのが仕事だった。
日本人が食うや食わずの時、この家に時々自動車で米俵や紙袋などが運ばれてきたし、魚や肉を焼く匂いがし、日本人のボロボロ服とは着ているものが違っていたという。
寮に届くべき余分の食材や衣料などは途中下車した親方のところにいったん消え、ここから寮に満足のゆく食料を届け不満が出ないようにしたようで、寮でトラブルがあったという話は聞かなかったと近くに住んでいた日本人は語っている。
また、別の地区の人で妻の家が韓国人の家と隣り合わせだった人は、惣菜をやり取りする関係だったし、防空壕も一緒に掘ったと語る。反感ももめ事もなく、協力し合う中であったということである。
なお、半田市内の国民学校(今日の小学校)の昭和17年までの児童数は1300人前後であったが、昭和18年から20年の間は1800人台に増え、翌21年は再び1400人台に減少している。
児童1800人台の時は、半田製作所や清水組(現清水建設で中島の工場建設請負)で働く朝鮮人保護者が345人おり、朝鮮人児童が412人国民学校に在籍している。
このことは単純に、昭和18年から20年の間だけ半島から子供を含む家族ぐるみ来た労務者が345世帯以上あったことを示している。
労務者が帰国(1945年9月から10月)する時は、貸切列車が何本も仕立てられ、駅頭で盛大な送別会があり、旅費は下関から釜山の船賃480円に加え、1人当たり1000円を下らない金額が支払われた。
ただ、給料もこの旅費も中島は親方に一括して払っており、一人ひとりに支払ったわけではない。個人への給料や旅費の支払いが十分でなかったならば、その責は日本側ではなく、人数さえ誤魔化していた韓国人側にあることは明確だ。
ところが、『統一評論』誌掲載の「中島飛行機半田製作所における朝鮮人強制連行と強制労働、空襲の実体」(金順愛・金貴東著)には、「動物輸送用の貨車に載せられ、外から鎖で施錠され」て連行され、工場では「空腹で仕事がはかどらないと棒で殴られ」、「一人が仕事をしくじると三十人全員がバットで殴られる」。
さらに、空襲時、「朝鮮人は防空壕に入れてくれない」から48人も即死したなどと書かれているという。
西氏はこの記述を「極端すぎる」としているが、実際のところ、上記に見たように学童も同行し、日本人工員から見ても羨ましいい魚肉さえ取れ、余裕のある生活であったのだ。
おわりに代えて:
徴用工は給与のほか精勤奨励金などももらっていた
本節は恒崎賢仁氏が提示した台湾人の父・鄭新発氏の徴用関連資料である。父は鄭成功の末裔であることに誇りを持ち、戦後の日本に居ついても鄭姓のままであったという。
台湾で徴用された鄭氏は三菱重工長崎造船所で働く。当時の給与や賞与金などの実物明細が示すように、細部まで明記されている(「給与+ボーナスも出ていた―父の『徴用工』資料が示す韓国の大ウソ」、『WiLL』2019年10月号所収)。
提示されているのは県知事から出された徴用令書、徴用工赴任心得(勤務先、ここでは長崎造船所作成)で、令書と一緒に配布されている。
出発時の服装、携帯品、宿舎、途中の食事も含め到着まで、しかも出発以降は県が派遣した引率者の指揮に従うことなどが詳しく書かれている。
給与のほかに、当時はグループ作業が通常だったので団体出勤賞や報奨金などが支払われている。
給与袋には賃料(給与)、請負利益金・奨励加給金、精勤奨励金、皆勤手当、生産増進慰労金、その他臨時手当、家族手当、忌引手当、兵事手当、休暇手当、防空手当、傷病手当など細分明記している。
他方で、所得税、健康保険、退職積立年金保険、立替金、下宿寮費、治療費、国民貯金などが差し引かれて現渡金となる。
1945(昭和20)年4月の賃料は85円43銭、利益金・加給金60円25銭、下宿寮12円、国民貯金17円などで現渡金は110円前後、今日に換算して20万円くらい。別資料であるが、当時はヒレカツが約1円の時代である。
大企業の記録には違いないが、徴用は国家的なものであり、賃金や手当などは職域で違いはあっても、会社の大小に関係なく基本的な線引きと記録の仕方などは大同小異ではなかっただろうか。
徴用令書は台湾人だけでなく朝鮮半島の人にも発出され、同様の処置がされたはずだ。
このことは、半田製作所での仕事と寮での暮らし、さらには帰国時の風景などからも確信を持って言えるのではないだろうか。
筆者:森 清勇
JBpress

























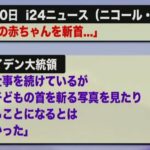
























この記事へのコメントはありません。