中国批判に猛抗議する留学生…アメリカの有名大学を侵食する「孔子学院」
中国批判に猛抗議する留学生…アメリカの有名大学を侵食する「孔子学院」
学習院女子大学の石澤靖治教授は自著『アメリカの情報・文化支配の終焉』にて、中国が世界に展開する工作機関「孔子学院」の実態に言及している。
米中対立は言うまでもなく、近年の国際情勢の動きはこれまでになく激しく、大きい。覇権国アメリカの世論、文化、情報支配が揺らぎ、あるいは崩壊しつつある。
その裏には「習近平の中国」の恐るべき工作機関である「孔子学院」の存在があった。学習院女子大石澤教授の自著『アメリカ 情報・文化支配の終焉』より、新たなメディア戦争を紐解く新たな概念「シャープ・パワー」を解説した一節を紹介する。
※本稿は石澤靖治著『アメリカ 情報・文化支配の終焉』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです
批判的な言論を封じ、好意的な勢力だけで周囲を固める「シャープ・パワー」
ハード・パワーとしての軍事力と経済力に対比させて、国家の文化的魅力として従来は、ソフト・パワーという言葉が使われていた。
ハード・パワーは、まさに力によって他国を強制的に自国に従わせるものであるが、ソフト・パワーとは、自国が本来持つ文化的魅力や政治的な価値、社会制度などのことである。
端的に言えば、ソフト・パワーとは世界から認められる国家の魅力ということができる。アメリカがこれまで覇権国として君臨することができたのは、ハード・パワーとともにソフト・パワーを兼ね備えていたからだ。
一方で、「シャープ・パワー」とは相手を説得するという「ソフト」なものではなく、相手を操作したり、話をすり替えたり、あるいは脅したりすることで、国際世論を自国に有利に展開するようにしようとするものだ。
シャープ・パワーとは外の言論は徹底的に締め上げ、自らに対する批判的な言論を封じ込め、自国に好意的な勢力で固めようとすること。
そして、そうしたことを実践してトータルで世論を誘導するために経済活動を利用し、他国のキーマンを経済活動を含めて取り込むこと、さらにこれらのことを民主主義体制の内部に入り込んでコントロールすることを指している。
これまでもやもやとしていた中国の行為が、この「シャープ・パワー」という明示的な言葉によって、はっきりとした形で認識されるようになったのである。
中国のシャープ・パワーの拠点「孔子学院」
中国はメディアという間接的な媒体へのテコ入れと同時に、中国語と中国文化を広めるための大がかりな仕掛けも作った。
それがその後の中国の戦略の焦点となる「孔子学院」である。
2018年12月の時点で世界154カ国・地域に、大学に設置される孔子学院548校、幼稚園児から高校生までを対象にした孔子課堂1193校が設置され、187万人が学んでいる。
このうちアメリカには100校を超える数の孔子学院が置かれ、孔子学院に比べて設置が容易な孔子課堂は500に上る。
当初はたんなる中国語と中国文化を普及させるための機関として見られていたが、現在、中国のシャープ・パワーの拠点として最も警戒されているのが孔子学院である。
というのは、孔子学院は中国政府から監督されコントロールされ、最終的には中国共産党中央宣伝部から監督されていることなどの実態が、次第に明らかになってきたからである。
オーストラリアで中国への批判的な言動に対して猛批判する中国人学生
オーストラリアにおける中国のシャープ・パワー戦略の展開で挙げられるのは、孔子学院と中国人留学生などによる大学への浸透などと並行してオーストラリア政治の取り込みを行ったことである。
そして、そのなかで言論の封じ込めという要素が連動してくる。中国がオーストラリアをターゲットにして、いかに文化・教育の交流を積極的に展開してきたかは、孔子学院の配置を見るとよくわかる。
オーストラリアにある大学の数は41だが、うち14大学に孔子学院が設置されており、じつにオーストラリアの大学の3分の1に孔子学院があるということになる。
また豪政府の統計によれば、2017年7月現在でオーストラリアに留学に来ている外国人留学生は56万4869人。うち中国出身者は29%で16万4000人。大学・大学院生は13万1000人であり、最大勢力である。
こうした状況が、たんに中国がオーストラリアでの中国語普及に関心をもっている、というだけなら問題はないわけだがそうではない。
中国に対して批判的な言動を行うと、猛烈な抗議と圧力を掛けてくる中国人学生の行為がオーストラリアで増えてきており、それに対する中国政府のアシストも同じように明確に見て取れるのである。
ある教授の中国に対する見解に不満を表明してネットで話題になった一人の中国人学生は、現地の領事館に定期的に招かれて歓迎された。さらにその際に、キャンパス内で中国人学生がどのような言動をしているか尋ねられたともいう。
中国マネーにからめ取られたオーストラリア
こうしたことは必ずしも中国政府の考えに納得していない他の中国人学生の、自由な言動を自粛させることにもつながっている。
他の事例では豪ニューカッスル大学で、ある教員が台湾を独立国として扱って発言したところ、中国人留学生がそれをひそかに映像に撮ってネットにアップして、「教室に3分の1いる中国人学生を不快にした」とつるし上げた。
またオーストラリア国立大学では、中国が警戒する法輪功(気孔を健康法として提唱するが、宗教的側面もある)の新聞が学内の薬局に置かれていたのを見つけた中国人学生が、そのことに抗議。激しい抗議に危険を感じたその薬局は新聞の撤去に応じることを強いられた。
こうした中国の弾圧に対して、オーストラリア政府が何らかのアクションを起こすのかと思いきや、オーストラリアの政治はすでに中国マネーにからめ取られていた。
オーストラリアにとって最大の貿易相手国である中国との経済関係は重要である。同時に、中国にとってもオーストラリアは太平洋において経済でも地政学的にも戦略的な価値があるため、とくにターゲットにしてきた国だ。
そうした中豪関係のなかで、オーストラリアの選挙資金制度は外国からの寄付・献金が合法であり、それがどこから来たお金なのか、どのように使ったのかなどを追跡することが難しく、透明性も低い。
アメリカやカナダ、ほとんどの欧州の国々ではその種の献金は広く禁じられているが、それがないオーストラリアには中国が関与できる余地を生んだ。
そして、そこから生まれた中国勢力の政治的な介入が同国における学問や言論の自由な活動を押さえ込み、中国の行為への批判的な発言を封じているのである。
中国批判に猛抗議する留学生…アメリカの有名大学を侵食する「孔子学院」
出典:石澤靖治著『アメリカ 情報・文化支配の終焉』(PHP新書)
中国のシャープ・パワー拡大をギリギリで阻止したアメリカ
孔子学院が「中国の実態を隠して、都合のいい姿だけをアメリカ社会に流布させるという危険な役割を担っている」として米政府が2018年2月に捜査に乗り出したのは、その行動に強い疑念をもっているからだ。
そして米議会も国際的な人権NGOであり、世界中の90カ国で人権の状況を監視しているヒューマン・ライツ・ウォッチも、2年間の調査で、中国政府の圧力がアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパの大学で学問的自由を損ねていることを確認している。
そして19年3月「海外での学問的自由を損なう中国政府の活動への抵抗」という提言を発表して、警告を発している。
「中国政府が、学問的自由に対する制限を国境を越えて行おうとしていることが判明した」としたうえで、すべての高等教育機関が行うべきものとして12の提言を行っている。
孔子学院を拒否すること、大学内における中国政府の干渉を徹底的に排除して学問の自由を守ること、妨害行為を各大学で厳しく監視すること、中国政府と関連した組織を監視すること、中国政府からの資金提供の実態を完全に明らかにすること、中国から来た学者や留学生に学問の自由を確保することなどがその柱で、中国からの侵害を完全に打ち破ろうという強い姿勢を打ち出している。
それまでも中国の行動に監視の目を光らせていたフロリダ州選出のルビオ上院議員は2018年2月、フロリダの5つの大学に中国政府との契約をやめるよう求める書簡を出した。
8月にはトランプによる国防権限法が成立。そして北フロリダ大学は、19年2月に孔子学院を閉鎖することを決めた。だが、それで状況は一気に転換するかどうかはわからない。
トランプ大統領の娘であるイヴァンカ・トランプ補佐官の娘が、春節の際に中国大使館で中国語の歌を披露したように、これまで10年以上にわたって拡大してきた孔子学院と500を超える孔子課堂は、アメリカ社会に一定レベルで浸透している。
17年に全米学者協会(NAS)は孔子学院の閉鎖を求めたが、それに対して従わない大学も多く、18年から19年に閉鎖を決めた大学があっても、19年4月現在まだ105校存在し、大きく減っているわけではない。
中国のシャープ・パワーが手をつけられなくなるほど拡大するぎりぎりのところで、アメリカはそれを阻止する行動を取った。しかしながら、それは最悪を免れたにすぎない。アメリカの情報・文化覇権は大きく揺らいでいる。
石澤靖治(学習院女子大学教授)
















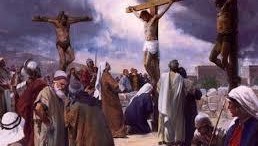

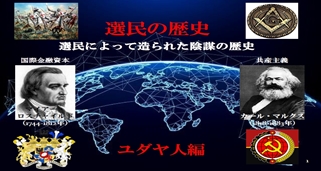
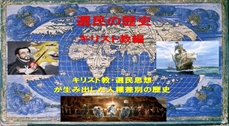
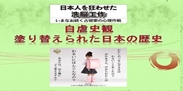




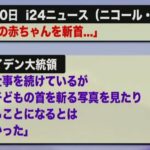
























この記事へのコメントはありません。