7/11(土) 6:01配信
限りなく北朝鮮化に向かう中国「1国2制度破棄」でサイは投げられた
紀元前49年、かねてからグナエウス・ポンペイウスと対立していたガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)がルビコン川を渡り、ローマ内戦は始まった。
当時のローマでは、ルビコン川を武装して渡ることは法で禁じられていたため、これを犯すことは宣戦布告を意味したのだ。
1月10日にルビコン川を渡る際、カエサルは「ここを渡れば人間世界の破滅、渡らなければ私の破滅。神々の待つところ、我々を侮辱した敵の待つところへ進もう『賽は投げられた』」と檄を飛ばしたと伝えられる。
要するに、重要な局面を超えてしまったら、もう後戻りはできないから、その後はひたすら「前進あるのみ」ということだ。
今回、中国共産党が「香港の1国2制度破棄」というルビコン川を渡ったのは明らかだ。習近平氏はかねてから「毛沢東崇拝」を隠しもしなかったが、習近平政権の毛沢東化はついに「ルビコン川」を渡ったと言える。
「香港国家安全維持法」が6月30日に行われた中国全人代常務委員会で可決されたが、施行されるまでこの法律の全文は公開されなかったという異常事態である。さらに、中文のみで英語のものはない。香港で施行される法律で英文がないものは初めてだろうと言われる。
逆治外法権
しかも、中国共産党の統治下にはいない国外の外国人(組織)にまで適用するという、言ってみれば「(逆)治外法権」のようなことも盛り込まれた。
一般的に治外法権は、外交官や領事裁判権が認められた国家の国民について本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。例えば、よくハリウッド映画で南米などの独裁国家の警察・軍隊から追われた、米国市民が大使館に逃げ込んで助かるというシーンがあるが、これが治外法権の活用である。
ただし、この場合の治外法権は「自国民」に対して適用するものであり、海外在住の外国人に自国の法律を強制的に適用するのは「逆治外法権」と言えるかもしれない。
もちろん現実的には、中国共産党に反抗的な人々(例えば私……)を、海外政府の協力を得ずに「公に」取り締まることはできない。
工作員などを使って取り締まったり、殺害することは可能である。実際に、オーストラリアでは、共産主義中国の情報機関が総選挙に立候補させようとしていた中国系男性(本人は断ったが……)が「謎の死」を遂げたことがTVで大々的に報道された。
とはいうものの、表立ってはできない。それぞれの国が統治しているからである。
しかし、一度でも中国共産党の統治下に入ったら(香港、大陸中国などに渡航したら)「令状無しの捜査」で、どのような罪をでっちあげられるかわからない。事実、これまでも多くの日本人が、不当な理由で拘束されてきた。
だから、香港だけではなく、中国大陸においても「民主主義」を大事にする(つまり中国共産党に批判的)外国人は危険にさらされる。ビジネスどころの騒ぎではなく、「民主主義国」の企業・国民はすべて撤退ということにもなりかねない。
日本では、いまだに媚中派銀が暗躍して「習近平国賓来日」をつなぎとめようと必死だが、ルビコン川を渡ってしまった「人類の敵」は、「もう2度と戻ってこない」のである。
第2次世界大戦は、ナチス・ドイツがポーランド(侵攻)という「ルビコン川」を渡ったから引き返せなくなり、世界の惨劇を招いた。
民主主義諸国も「ルビコン川」を渡った
ポーランド侵攻でルビコン川を渡ったのはナチス・ドイツだけではない。あっという間に占領されたフランスはもちろん、ナチスのロケット攻撃などに苦しめられた英国も、それまでの「融和的態度」をかなぐり捨て「ナチス・ドイツという『人類の敵』を、どのような犠牲を払っても殲滅するまで戦う」という誓いを立てたことで「ルビコン川」を渡ったのだ。
英国において、媚ナチ派であったネヴィル・チェンバレンが退陣し、対ナチ強硬派のウィンストン・チャーチルが彗星のごとく現れたのは象徴的である。
注意しなければならないのは、ナチス・ドイツが「ポーランドというルビコン川」を渡るまでは、世界的に媚ナチ派が主流であったことだ。特に米国の経済界では、「ナチス・ドイツは上客」だという扱いをしていた。
まさに、これまで世界で媚中派が大きな勢力を持ってきたのと同じことが起こっていたのだが、ほとんど一夜にして流れが変わった。
「香港というルビコン川」を渡った共産主義中国もすでに、ナチス・ドイツ同様「殲滅すべき人類の敵」と認識され始めている。
つまり、ルビコン川を渡ったのは中国共産党だけではなく、「どのような犠牲を払っても『人類の敵』を殲滅する」覚悟を決めた西側先進諸国もルビコン川を渡ったのである。
「人類の敵の実力」は?
第2次世界大戦の「人類の敵」ナチス・ドイツを殲滅するには、1939~45年まで6年の歳月が必要であった。強大な米国が参戦してもそれほどの時間がかかったし、それまでの欧州勢だけの戦いでは極めて旗色が悪かった。
ドイツの技術力が突出していたのがその大きな原因だ。それを端的に示すのが、宇宙ロケットである。戦後、米ソ両大国は宇宙開発競争にしのぎを削ったが、そのロケット技術のほとんどすべては、敗戦国ドイツから引き連れてきた技術者が提供したものである。
ロンドン市民を苦しめたV-2ロケットのような先端ロケット兵器はどこの国も保有していなかったのだ。
また、世界で初めてジェットエンジン(ターボジェット)の推進力だけで飛行したのは、ドイツのハインケルによって開発されたHe178である。さらに、初めて航空機同士の交戦を行った実用ジェット戦闘機はドイツのメッサーシュミット Me262だ。
さらに、日本に最大級の不幸をもたらした原子爆弾の製造を米国が急いだのは、ドイツで核兵器の開発を行っているとの情報をつかみ、先を越されたくなかったからである。
したがって、強敵であるナチス・ドイツを倒すために共産主義の危険性がわかりながらも「毒で毒を制す」手法を採用したのも仕方がない面がある。
共産主義中国は、いわゆる軍事力ではナチス・ドイツほど恐ろしくはないというのが私の判断だ。特に核兵器に関しては、ロシア(ソ連)にも劣る。さらに、人民解放軍は人民を抑圧するための組織で、養わなければならない兵隊の数は多いが、外国と戦うための戦力にはあまりならない。
実際、自慢のたった2隻の国産空母のうち、「遼寧」は、未完成の艦体を中国がウクライナから購入して完成させたものである。また。2019年末には、本当の意味での初めての国産空母「山東」が就役したが、実のところはマスクや人工呼吸器に代表されるような「中国品質」ではないだろうか?
共産主義中国の恐ろしさはトロイの木馬作戦
このように、軍事的側面で考えれば、共産主義中国はナチス・ドイツほどの脅威ではないが、恐ろしいのは「工作活動」である。
ZTEやファーウェイ、TikTokズームに加えてサイバー攻撃など、電子ネットワークにおける中国の工作活動は西側先進国には到底太刀打ちできない水準である。共産主義中国のWTO加盟が2001年だから、それ以来おおよそ20年間にわたって「安いから」と中国製品を次々と導入してきたつけを払わされているのが西側先進諸国だ。
「安いのにはわけがある」という言葉が思わず頭に浮かぶ……
ようやく、ファーウェイ製品などの導入に制限をかけるようになってきたが、ネットワークの隅々にまで浸透した中国製品の完全排除は難しく、リスクは長期にわたって残る。
さらに我々にとって脅威なのは、2010年から施行された共産主義中国の「国防動員法」である。中国共産党賀が「有事」と判断すれば、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性に対して国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導するなどの内容が含まれた法律だ。
この法律には海外在住者を除外する規定は見当たらない。つまり、日本に多数在住する共産主義中国の人々も、この法律から逃れることができないであろうということだ。いくら親日的な人でも「国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われる」と規定されていれば従わざるを得ない。
習近平に与えられた2つの選択枝
冷戦時代、2大強国として米国と並び立っているように見えたソ連邦は、実は異常に軍事に費用をつぎ込んだ経済的にはボロボロの張り子の虎だということが、崩壊した後明らかになった。
共産主義中国の鄧小平は、そのソ連の姿に自国の未来と恐怖を感じ、強力に「改革・解放」を押し進めた。そのおかげで、中国は経済的に繁栄しソ連邦のような崩壊から逃れることができたが、2019年1月9日の記事「客家・鄧小平の遺産を失った中国共産党の『哀しき運命』を読む」で述べたように、習近平氏は「香港1国2制度破棄」というルビコン川を渡り、毛沢東暗黒時代へ回帰する道を選んだ。
こうなると、習近平氏(中国共産党)には
1) 毛沢東時代の「北朝鮮のような」貧しい鎖国をする国になる
2)「人類の敵」として世界中の先進国から攻撃を受け滅亡する
のどちらかの道しか残されていない。
中国が、ここ数十年驚異的な発展を遂げることができたのは「改革開放」という資本主義・自由主義的政策を共産主義の枠の中であっても採用したからだ。そして、その共産主義の中のささやかな自由の象徴が香港であった。
言ってみれば、「改革・開放政策」が、中国大陸の中での「1国2制度」であったのだ。香港の1国2制度を破壊すれば、当然中国大陸の1国2制度である「改革開放」も死を迎える。
「改革開放」が存在しない中国大陸は、北朝鮮と何ら変わりがない。習近平氏の運が良ければ、北朝鮮のように貧しい国で王朝を築くであろうが、毛沢東時代と違って「自由と豊かさを知った」中国人民を押さえつけるのは至難の技である。
かなりの確率で、習近平政権は崩壊せざるを得ないと考えるが、中共(武漢)肺炎対策で人気を博した李克強氏が「第2の鄧小平」になる可能性はどれほどあるのだろうか?
大原 浩(国際投資アナリスト)

























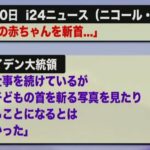
























この記事へのコメントはありません。