7/10(金) 6:46配信
習近平の大失敗…香港併合の悪手で世界制覇の「最強カード」を失った
前々から不思議だった。中国は日本の「帝国主義」や「侵略」を徹底的に弾劾するのに、なぜ、英国との「阿片戦争」については一言も言わないのか?
日中戦争はまだ起こってから80年ほどだが、阿片戦争はすでに180年も経っているからか。日本を責め立てれば物質的に大いに得るものがあるが、英国を責め立てても何の得にもならないからか。
【写真】「日本のどこがダメなのか?」に対する中国ネット民の驚きの回答
日本人がアメリカに原爆を落とされても抗議しないように、中国人も欧米人の横暴に対しては甘いのか。日本人への憎悪は主に、同じアジア人に負かされたという恨みから来ているのか……などといろいろ考えたが、よくわからなかった。
ところが最近になって、これが正解かというのを思いついた。おそらく彼らは最終目標に向かって、順を踏んでやっているだけなのだ。最終目標というのは、もちろん世界制覇。
その目標を達するためには、前線の拡大は得策ではない。だから、まずは一番簡単そうな日本を片付ける。「南京虐殺」などの情報を広め、日本がアジアを残忍に侵略したというイメージを世界に定着させ、そのうち尖閣諸島を奪っても、これは元々中国の領土であったと言い張れる土壌を作る。
と同時に、日本の政治家や経済人を取り込み、日本の土地も企業も買収する。そして、やがて日本が抵抗しなくなったら、次は台湾とその他のアジア。
いずれにしても、その間は欧米は味方につけておく。しかし、アジアが済めば、次はヨーロッパで、最後はアメリカというのが、おおよそのシナリオではないか。だとすれば、遅くともヨーロッパに取り掛かったところで、中国政府は阿片戦争というカードを引っ張り出す可能性がある。
世界制覇への野心が露わに
イギリス軍艦「HMSコーンウォリス」号内で締結された南京条約(Wikipediaより)
阿片戦争は、英国とインドと清との三角貿易に端を発する。
英国は清から、お茶、絹、陶磁器などを大量に輸入し、重篤な輸入超過に陥っていた。しかし、その支払いに銀を使うことを嫌い、そこで考え出したのが、インドで作った阿片を清に密輸することだった(清は阿片の輸入を禁止していた)。
イギリスが清に売った阿片の総量は8000万トンと言われる。阿片は、末端ではグラム単位で取引されるのだから、8000万トンとは途方もない量だ。イギリス人はその支払いに銀を要求したため、清から大量の銀が流出した。
そこで1838年ごろから、清当局における真剣な取り締まりが始まり、英国は利益を失う。そのときの抗争が戦争に発展、最終的に英国が清を負かす。不義の戦争と呼ばれる阿片戦争だ。
そのあと結ばれた講和条約は激しく不平等で、賠償金や治外法権のほか、香港を含む5つの港も英国のものとなった。それを見たヨーロッパのその他の列強も、我も我もと清の解体に取り掛かった。
つまり、こういう経緯を振り返れば、たとえ180年経った今でも、「香港は元々中国の領土だったのに大英帝国が不当にも奪った」、「なぜ、その返還を99年間も待たねばならないのか」と中国が主張すれば、国際世論はガサッと動くかもしれない。
中国人というのは、遠大な計画を立てたら、機が熟すのをじっと待てる人たちだ。
1950年代の終わりに始まった大躍進政策は大失敗し、国内が混沌とした。そして、それを埋め合わせるはずだった文化大革命が、さらなる混乱を招いたのだが、すごいのは、10年後にようやく文化大革命が終息したとき、見渡す限りの荒廃の中で、いつか将来、中国を世界一の国にしようと考えた人たちが存在したことだ。
そして、それ以後、中国はその目的に向かって確実に歩を進めてきた。歩みはもちろん完璧ではなかった。汚職、人権蹂躙、貧富の格差、権力闘争……。しかし、どんな障害があっても、たとえ遅々とした歩みでも、彼らはちゃんと前進してきたのだ。
ところが、習近平主席が権力を握って以来、計画は次第に狂い始めたようだ。これまでの中国では、一人の人物に権力が集中することはなかった。彼らは第二の毛沢東を欲していなかったのだろう。
なのに、習近平は中国のその一党独裁システムを、一人独裁システムに変えて、まさに第二の毛沢東の道を歩んでいる。しかも、中国のこれまでの指導者が決して露わにすることもなかった世界制覇の野心が、突然、誰の目にもはっきりと見えるようになった。
さらに香港では、抑圧という世界中の非難を招く方法を選んだ。なぜか?
本来なら、阿片戦争の「犯罪性」や、「香港を奪われた経緯」をじっくりと説いて、欧米を味方につけることさえ不可能ではなかったはずなのに、急ぎすぎた習近平は、そのチャンスを永久に棒に振ってしまった。
隘路にはまる習近平
毛沢東のあと、鄧小平が編み出し、後進が育んできたせっかくの長期戦略が、習近平のせいでガラガラと壊れようとしている。それと同時に、多くの国が中国を危険視し始め、中国がこれまで絶対に避けてきた全方面への戦線拡大が、すごいスピードで進んでいる。
これまでの一党独裁制では、常に権力闘争があった。それが、あたかも二大政党制のような監視システムとして機能していたのかもしれない。しかし、習近平の一人独裁ではそれがなくなり、攻撃的な一帯一路政策も、専制的なアジア統治計画も、米国との危険な闘争も、そして、不毛なプロジェクトにまつわる膨大な出費も、誰も止めることができなくなった。
そして、そこに落ちたのが新型コロナウイルスという爆弾だ。まだその余熱も冷めないうちに発せられた「中国が世界に先駆けてコロナを克服した」とか、「中国が世界を救済した」という言葉。それを世界は受け付けなかった。
コロナの発信地である中国、しかも初動を誤った共産党政府が、自国のコロナ対策の素晴らしさを説くことの弊害について習近平に進言する人すら、もう、一人独裁の国にはいなかったのか。
そのコロナのせいで、この10年間、未曾有の伸びを示し続けた中国経済が、風船が萎むように縮小している。
鄧小平以来、さまざまな欠点にもかかわらず、中国の国民が政府に付いてきたのは、生活が年々豊かになったからだ。13億の国民を食べさせていくのは並大抵のことではない。それを首尾よくやってきたのがこれまでの中国政府だったのに、もし、各地で「米よこせデモ」などが盛り上がれば、どうなるのか。
中国政府が本当に怖がっているのは米国ではなく、13億の自国民だ。
だからこそ、ひとまず敵は日本だけにしておくはずだったのに、中国の敵の輪にはすでに手強い米国が加わっている。
しかし、今更コースを修正しようとすれば習近平の面子が潰れるし、これまで通りの攻勢を掛ければ、世界における中国の政治的、経済的オプションは狭まる。習近平は今、隘路にはまり込んでいる。
そんななか、中国と仲のよいドイツ政府が、重要物資の中国全面依存を見直し、中国資本によるドイツ企業の買収は阻止するというのは建前の話で、産業界は一刻も早く中国への輸出を復活させようと死に物狂いだ。
ただ、ドイツの技術が中国のそれよりも優位であったこれまでは中国は従順だったが、両国の技術力が互角になったとき、彼らがなおも従順である保証はない。いつか裏切られるかもしれないと薄々感じながらも、それでも中国に縋るドイツを、アメリカは冷ややかな目で眺めているのではないか。
そんなドイツの姿から、日本が学ぶものは多いように感じている。
川口 マーン 惠美(作家)





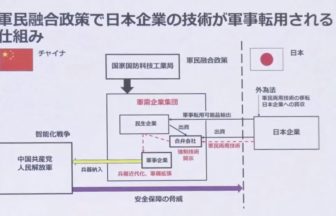



















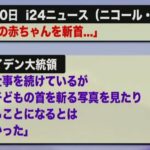
























この記事へのコメントはありません。