・イギリスのアジア侵略
インド産の手織り綿布がヨーロッパで大流行となり、インドでの覇権を確立したイギリスはイギリス東インド会社を設立し、インド侵略の母体としました。
1796年にスリランカを併合したイギリスは、19世紀を通じてインド・ビルマ・マレー半島の植民地化を進めました。
イギリスが本当に狙っていたのは中国(清朝)だったため、ビルマ全域を支配下におくことで一気に中国侵略の道が開けました。
イギリスが中国を侵略するために利用したのがアヘンでした。イギリスは清にアヘンを密輸し、清が規制すると貿易の自由が侵されたと言いがかりをつけ、1840年清に戦争を仕掛けました(アヘン戦争)。アヘン戦争に敗れた中国はこれ以降、欧米列強への従属を深めていくことになります。
イギリスは東南アジアでも足場を固め、1824年にペナン・シンガポール・マラッカのマレー半島に英領植民地を確立しました。マレー半島全域の植民地化に成功したのは1896年です。
・イギリスのインド統治
インドでイギリスは国家としてケシの栽培を強制し、アヘンの製造・輸出に励みました。
またインドに強制的にイギリス式の法律を施行し、税金を払えない農民たちの土地を奪い、食糧を作るべき田畑は減少し、大飢饉が頻発するようになりました。
ことに1770年に起きたベンガル地方の大飢饉では、1000万人もの死者が出ています。
インドで起きた大きな飢饉は Wikipedia によると次の通りです。
1800~1825年にかけて大飢饉が5回発生し、死者約100万人。
1826~1850年に大飢饉2回で死者約40万人。
1851~1875年に大飢饉6回で死者約500万人。
1876~1900年に大飢饉18回で死者約1600万人。
1943年のベンガル飢饉の死者約300万人。
1943年のベンガル飢饉に際して、インド独立後の初代首相に就任したネールは、次のように述べています。
「幾世代にもわたったイギリス支配のあげくにおける貧しさと醜さ、そして人間的堕落の全貌をさらけ出して見せた。それがインドにおけるイギリス支配の行き着いた頂点であり、結実であった」
インドの農民たちのあまりにひどい暮らしぶりを見たナイチンゲールは、こう語っています。
「東洋における、いな世界におけるもっとも悲しい光景は、私たちのもつ東洋帝国(イギリス領インド帝国)の農民の姿である」
・インド綿工業の壊滅
17世紀までインドは世界一の綿製品国でした。インドの職人が手工業で作る綿製品は、世界中で愛用されていました。
しかしイギリス産業革命による安価な綿製品に駆逐され、あっという間に衰退しました。
イギリスはインドの綿製品を駆逐するために、ありとあらゆることを行いました。
輸入税では、インド綿を輸入するに際してイギリス本国ではモスリン37.2%、キャラコ67.5%という高額な輸入税をかけましたが、インドがイギリスの綿製品を輸入する際にはわずか2.5%の輸入税をかけるだけに留めました。
綿花の仕入れでは、インド人が綿花を仕入れる際には、国内消費税の1割を植民地政府(イギリス)に納めなければいけませんでした。一方、イギリス人が綿花を手に入れる際には、租税も関税も支払う必要がありませんでした。
鉄道の輸送費も高額に設定され、インド国内での輸送賃金が、イギリスへの輸送賃金よりも高く設定されました。
1俵の綿花を運ぶのにカルカッタから日本までが100円、カルカッタからボンベイまでが75円、ボンベイから英国のリヴァプールまでは15円で輸送することが出来たのでした。
(「GHQ焚書図書開封10: 地球侵略の主役イギリス」西尾幹二著、徳間書店)
しかしイギリスの蛮行はこの程度ではとどまりませんでした。
「どうしても紡績工場を去らず、飽くまで紡績業のために働くと頑張った印度人の職工たちに対し、再び仕事が出来ないようにと、その五本の指を切断したと言ふ非道極まる事件である。職を失った数万の紡績工が農村に帰っても耕す土地がなく、飢餓と貧困のどん底に叩き落とされ、人生の生き地獄に呻吟する身となったことは、到底許すベからざる罪悪であらう。」(「インドの叫び」ボース・ラスビハリ著、三教書院)
「文化勲章の経済学者・宇野弘文教授は近年こう語っています。『インドの職人がつくるモスリンは非常に繊細な織物で、産業革命の技術でもできなかった。そこでイギリス政府は軍隊をインドに送って、モスリンを織る村の男子の両手首を全部切り落とした。僕の親しかったインド人の学生も、生まれた村はモスリンの名産地だったが、全部手首を落とされたと言っていた』(雑誌『自由思想』117号)。こういう話は一例とされています。」(「日本人らしさの発見―しなやかな〈凹型文化〉を世界に発信する」芳賀綏著、大修館書店)
・インドは自由を求めて反乱を起こした
イギリスの過酷な圧政に対して、1857年から1859年にかけて、イギリスの植民地支配に対する民族的反乱(インド大反乱)が起きています。インドでは「第一次インド独立戦争」と位置づけられています。
インドの各地に反乱政権が生まれ、イギリス軍をインドから追い出すべく立ち上がり、すべての反乱が鎮圧されるまでに1年以上を要しました。
反乱が治まった後のイギリスによる報復は、言語を絶するほどに過酷でした。
イギリスの歴史家ジョージ・ブルース・マレソンは著書「インド反乱史」のなかで、次のように綴っています。
「戒厳令は布かれた。血腥(ちなまぐさ)き反乱に荷担したもののみならず、老人、女子、小児なども血祭りに上げられた。彼らは村々において焼殺、または銃殺された。英人は臆面もなくこれらの残忍を誇って、あるいは一人の生者を余さずと言い、あるいは黒ん坊どもを片端から殴り飛ばすのは実に面白い遊戯だと言い、あるいは実に面白かったと言い、または書いている。このようにして六千の生霊が屠られたとある」
「我が軍の将校はすでに各種の罪人を捕え、あたかも獣を屠るがごとくこれを絞刑に処していた。絞首台は列をなして建てられ、老者・壮者は言語に絶する残酷なる方法をもって絞首された。
ある時のごときは、児童等が無邪気に兵の用いし旗を押し立て、太鼓を打ちながら遊んでいるのを捕えて、これに死刑の宣告を与えた。」
(「日米開戦の真実 大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」佐藤優著、小学館文庫)
インドがイギリスの支配を断ち切るために立ち上がった独立戦争は、幼子まで含むインド人の虐殺をもってあがなわれたのです。以後、イギリスが命じるままにインドの若者の多くはイギリスの戦争に駆り出され、命を落とすことになります。
第1次世界大戦で戦死したインド兵だけでも67,000人、負傷者も67,000人とインド議会において報告されています。
・ローラット法とガンディーによる不服従・非暴力運動
1919年、イギリスは高まる一方のインド独立運動を抑えるために一種の治安維持法にあたるローラット法を施行しました。
嫌疑あるインド人に対し逮捕状なしに逮捕でき、弁護人も証人も控訴も認めず、秘密審理によって告発事項以外の罪も宣告できる、体制側のやりたい放題の、インド人の人権はまったく考慮されていない法律でした。
このような理不尽な法律を押しつけられたことで、インド人の怒りは頂点に達し、マハトマ・ガンディーによる不服従・非暴力によるイギリスへの抵抗運動が始まりました。
この法律とガンディーが逮捕されたことに抗議するため、パンジャブ地方のアムリットサールに集まっていた非武装の2万人に対し、イギリス軍が発砲しました。射撃は全弾が尽きるまで10分間継続されたと証言されています。
死者1200名、負傷者3600名と報告されています。
発砲を指示した指揮官は英国軍事会議にかけられましたが、罪に問われることはありませんでした。そればかりかイギリスの功労者として讃えられ、一般人から募った2万ポンドが贈られています。
虐殺の後に待っていたのは恐怖政治でした。虐殺と恐怖政治は通常、西欧列強がアジアを植民地にした直後に決まってとられる政策ですが、それが20世紀初頭においても行われていました。
1921年より37年までに25万人が投獄され、3000人が銃殺されたと記録されています。10歳や11歳の少年たちがイギリス国王に謀反の気持ちをいただいているとの理由により、終身刑を言い渡されたとも書籍には綴られています。







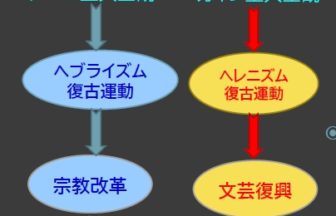
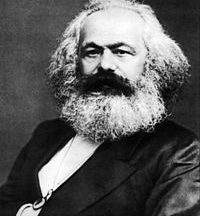
















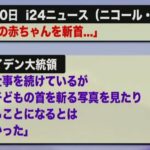
























この記事へのコメントはありません。