デイリー新潮 8/6(日)
長崎への原子爆弾投下に伴い発生したキノコ雲 (画像出典:Charles Levy, Public domain, via Wikimedia Commons)
「とっくに白旗をあげてよかった状況だったのに、日本軍が抵抗しつづけたから、アメリカが開発した原爆を投下したのだ。戦争終結のためには仕方が無い。そもそも日本が間違った戦争をしかけたのが原因だ」
【この記事の写真を見る】日本人を「けだもの」と呼んだアメリカ大統領
日本人の多く、あるいは新聞やテレビに顕著に見られるこうした歴史観が、まったく事実に基づかないものであることは、前編でご指摘した通りだ。しかし、こうした歴史観がいまだにはびこっているために、原爆投下を正当化する向きは存在し続けている。映画「バービー」がPRに際して原爆投下をお笑いのネタのように扱ったことはそのことを明るみにしたともいえるだろう。
残念なことに、日本人でも原爆投下のプロセスを正確に知る人は多くない。特に日本人が知らない重要なポイントとして、以下の4つを挙げたうえで、前編では(1)、(2)について詳しくご説明した。
原爆によって破壊された広島の街。広島・平和祈念展示資料館の展示より
(1)原爆はアメリカの単独開発ではなく、イギリス、カナダとの共同開発である。
(2)原爆の投下はアメリカだけで決められるものではなく、イギリス、カナダも同意していた。
(3)原爆を大量殺戮兵器として使う必要はなかった。
(4)科学者たちは投下前から核拡散を憂慮して手を打とうとしたが、アメリカやイギリスの政治家たちがそれを無視した。
後編でも、『原爆 私たちは何も知らなかった』(有馬哲夫・著)をもとに、(3)、(4)について見ていこう(以下、引用はすべて同書より)。
現代人、特に広島と長崎を経験した日本人にとって原爆は大量殺戮兵器そのものだ。しかし、実のところ原爆を開発し、使用しようとしていたアメリカには様々な選択肢があった。有馬氏は以下のように論点を整理している。
「『原爆を日本に使用すると決定した』イコール実際に広島や長崎に投下されたように、『女性も子供も沢山いる人口が密集した都市に無警告で使うことを決定した』のだと捉えられがちです。
事実は、そうではありませんでした。日本に使用するといっても、大きく分けて三つの選択肢が存在しました。
(1)原爆を無人島、あるいは日本本土以外の島に落として威力をデモンストレーションする。
(2)原爆を軍事目標(軍港とか基地とか)に落として、大量破壊する。
(3)原爆を人口が密集した大都市に投下して市民を無差別に大量殺戮する。
また、使用するにしても、二つの方法がありました。
(A)事前警告してから使用する。
(B)事前警告なしで使用する。
(1)の使い方ならば、絶大な威力を持ってはいるが、ただの爆弾だということになります。実際、ビキニ環礁などで実験した水爆がそうです。
(2)ならば大量破壊兵器になります。
(3)ならば大量殺戮兵器になります。しかも、戦争に勝つことより大量に殺戮することを優先しているので当時の国際法にも違反していますし、人道に対する大罪です。
ただし、(3)と(A)の組み合わせならば、警告がきちんと受け止められて退避行動がとれるなら死傷者の数をかなり少なくできる可能性があり、大量破壊兵器として使ったとはいえても大量殺戮兵器として使ったとはいえなくなるかもしれません。国際法もぎりぎりクリアしていたといえるでしょう。
(3)と(B)の組み合わせならば、まごうかたなく無差別大量殺戮であり、しかも無差別大量殺戮の意図がより明確なので、それだけ罪が重くなるといえます」
この選択肢、そして最悪の(3)(B)の問題点については、当時の意思決定に関係した暫定委員会のメンバーやアメリカのバーンズ国務長官、そしてトルーマン大統領も十分理解していた。さらに、「事前警告なしの使用には同意しない」と米海軍次官は文書で政府に伝えている。
「特に軍人は、(3)と(B)の組み合わせをできるだけ回避しようとしました。戦争といえども一線を越えていることは明らかなので、たとえ戦争に勝ったとしても、他の国の軍人たちから後ろ指を指されることになります。こんな不名誉なことをしなくとも彼らは圧倒的に優位に立っていて、日本の敗戦は時間の問題だったのです。自らの軍事的栄光を不名誉な行為で汚したくはないというのは当然でしょう」
アメリカと共に原爆を開発し、投下に同意を与えたイギリスのチャーチル首相は(2)(A)の使用法を考えていたという。開発に関わった科学者たちも、決して大量殺戮を実行したかったわけではない。
それではなぜ、結局、アメリカは、当時のトルーマン大統領は(3)(B)の形で原爆を使用することにしたのか。
日本人は「けだもの」
『原爆 私たちは何も知らなかった』ではその理由や経緯について詳述しており、ここではとてもすべては紹介できないので、もっともわかりやすい理由を一つだけ挙げておこう。それはトルーマン大統領の人種偏見だ。
「戦争に勝つためなら、大量破壊兵器として使うので十分なのに、わざわざ大量殺戮兵器としての使い方を選んだ理由は、トルーマンとバーンズ(国務長官)が日本人に対して持っていた人種的偏見と、原爆で戦後の世界政治を牛耳ろうという野望以外に見当たりません。
トルーマンは、ポツダム会談でチャーチルと原爆のことを議論したときも、原爆投下のあとの声明でも、サミュエル・カヴァートというアメリカキリスト教協会の幹部に宛てた手紙でも、繰り返し真珠湾攻撃のことに言及しています。この点は見逃せません。
つまり、真珠湾攻撃をした日本に懲罰を下したかったのです。真珠湾攻撃が彼の復讐心を掻き立てるのは、被害が大きかったというよりも、自分たちより劣っているはずの日本人がそれに成功したからです。これは根拠のない推論ではありません。
トルーマンは若いころ(正確には1911年6月22日)、のちに妻になるベスに送った手紙のなかでこのようにいっています。
『おじのウィルは、神は土くれで白人を作り、泥で黒人を作り、残ったものを投げたら、それが黄色人種になったといいます。おじさんは中国人とジャップ(原文のママ。日本人の蔑称)が嫌いです。私も嫌いです。多分、人種的偏見なんでしょう。でも、私は、ニガー(黒人のこと)はアフリカに、黄色人種はアジアに、白人はヨーロッパとアメリカに暮らすべきだという意見を強く持っています』
大統領になってもこの人種的偏見から抜け出せていなかったことは、彼が前述のカヴァート宛の手紙で『けだものと接するときはけだものとして扱うしかありません』と記していることからもわかります。彼が『けだもの』と呼んでいるのは『ジャップ』のことです。人種差別が厳然としてあった当時としても、大統領の言葉として著しく穏当を欠いた言葉です」
日本人を「けだもの」と考えていたアメリカ大統領にとっては、いくら日本人が死のうが知ったことではなかったし、新兵器の威力を世界に誇示するにはむしろ好都合だったということである。
もっとも、こうした選択をしたことで、アメリカは自らの首を絞めることになる。その後の果ての無い核拡散、核開発競争は、結果的に世界を危機に追い込んだだけだとも言えるだろう。
予言の書
実は、原爆投下が決定される前に、科学者たちからアメリカ陸軍長官あてに1通のレポートが提出されていた。「フランク・レポート」と呼ばれるこのレポートの中には、日本への原爆投下を思いとどまるべきだ、といった進言が書かれているが、その先見性には目を見張るものがある。
ここで科学者たちは、原爆の情報をアメリカが独占するのではなく、オープンにして国際管理を進めるべきだ、とも主張している。
科学技術の独占は極めて困難なので、結局のところ、いつか敵国にも共有されることになる。それならば先手を打ってソ連などが開発できていない現時点で、仲間に引き込んでしまって、世界でこの兵器を管理してしまうほうが現実的だ、という論理である。
さらに、レポートにはこんな一節もある。
「デモンストレーションであれ実戦使用であれ、原爆をいったん使用したらその時から原爆開発・軍拡競争が始まる。世界の各国はあらゆる資源と技術をためしてより威力のある原爆をより効率的に安価に数多く作ることに取り組む。さもなければ、自国を守れないからだ」
このレポートは「予言の書」と言ってもよいほど現在の世界状況を言い当てている。しかし、こうした訴えも、「ジャップを懲らしめる」というトルーマンの考えを変えるには至らなかった。科学者も軍人も、理性を働かせて説得に動いたが、結局、原爆は広島、長崎に投下されたのだ。
有馬氏は、同書の中でこう訴えている。
「現在核保有国のトップになっている大統領、元首、首相の顔を思い浮かべてみましょう。
彼らはトルーマンより、ましでしょうか。
このような過ちを犯しそうになく、人間的欠陥もなさそうでしょうか。彼らの周囲には優秀な閣僚、側近、官僚、科学者はいるでしょうか。そうだとして、国家のトップたちは、彼らの英知に素直に耳を傾け、常に理性的な判断ができるでしょうか。
だとすれば、私たちは、自ら戦争をしかけず、平和を祈っていれば、二度と原爆の災禍に遭うことはないでしょう。原爆死没者も安らかに眠ることができると思います。
そうではないと思うのなら、今まで疑ったことがないものを疑い、考えたことがないものを考え、したことがないことをしてみなくてはなりません。
同じことを繰り返していては、いつヒロシマ・ナガサキの過ちが繰り返されるかわかりません」
この警鐘は、ロシアが核の使用をほのめかしている今、一層重く響くのではないか。
※有馬哲夫『原爆 私たちは何も知らなかった』(新潮新書)から一部を再編集。













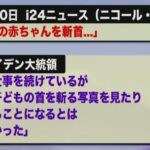

この記事へのコメントはありません。